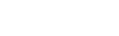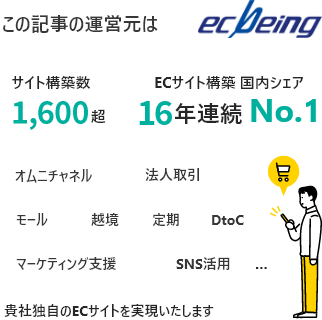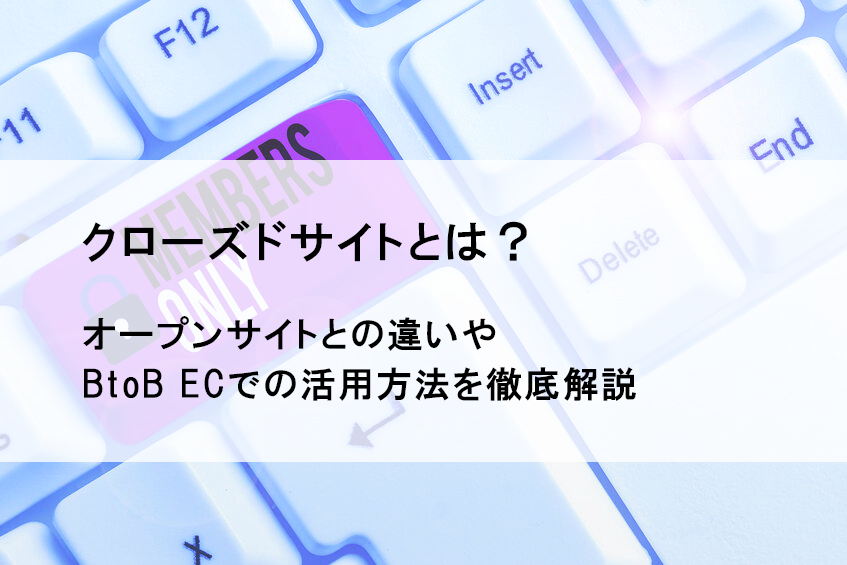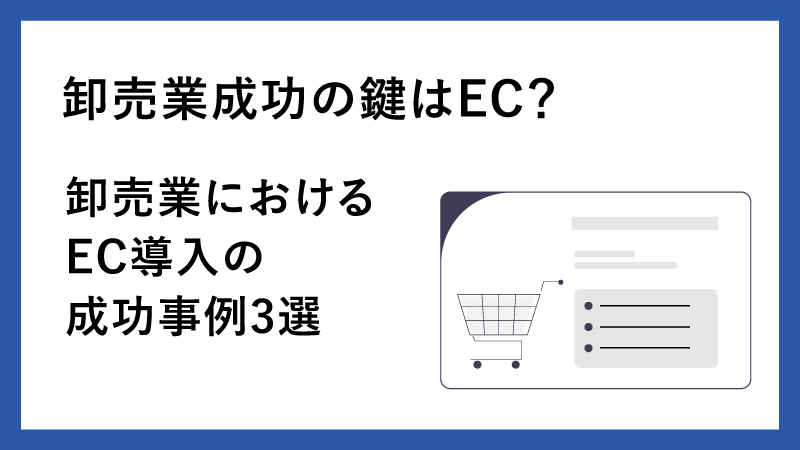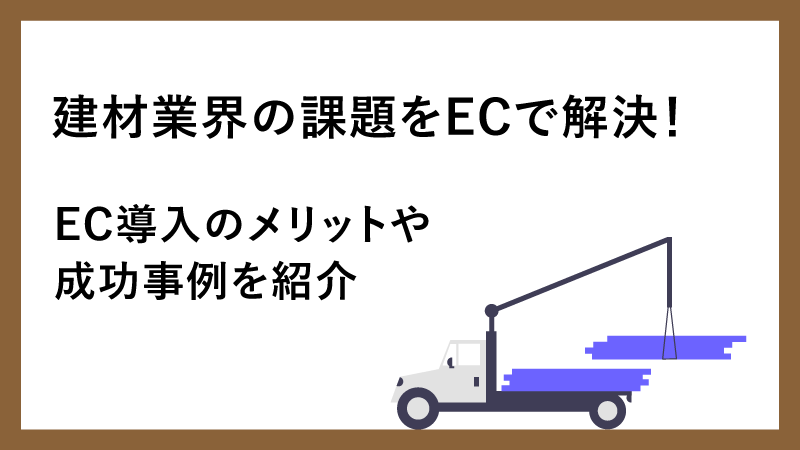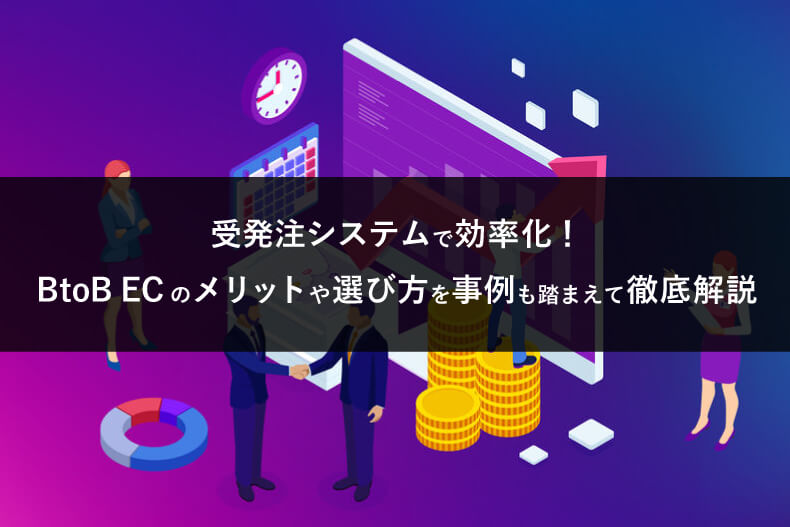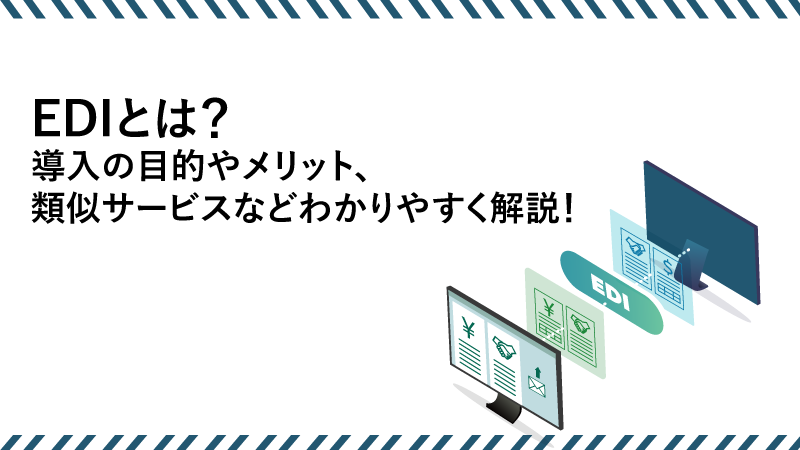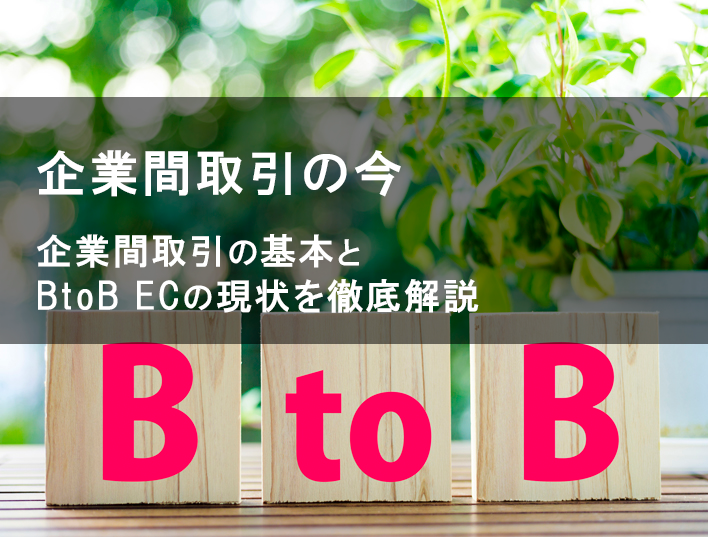- BtoB TOP
- BtoB ECノウハウ記事
- 【建設業のDX】受発注システム導入ガイド|アナログ業務から脱却し利益を最大化する方法とは?
【建設業のDX】受発注システム導入ガイド|アナログ業務から脱却し利益を最大化する方法とは?
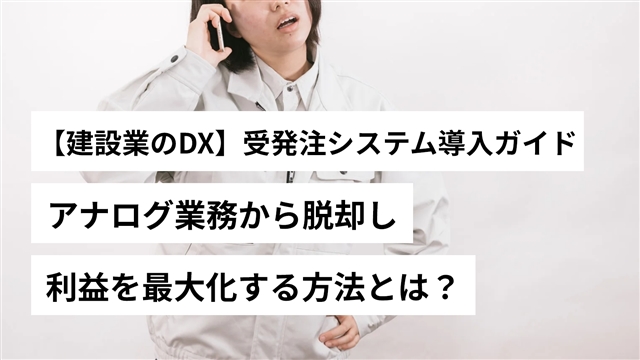
「協力会社とのやり取りが電話やFAXばかりで、言った言わない問題が起きがちだ…」
「現場ごとに違う資材の見積もりや発注書の作成に、膨大な時間がかかっている」
「過去の取引価格をExcelで探すのが大変で、見積もり作成が属人化している」
建設業界で受発注業務に携わるご担当者様の中には、このようなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
人手不足や働き方改革への対応が急務となる中、旧来のアナログな業務プロセスは、生産性の低下やヒューマンエラーの温床となり、企業の競争力を少しずつ蝕んでいきます。
こうした状況を打破する鍵として、今「受発注システム」の導入に注目が集まっています。
今回は、建設業における受発注システムの導入に関するさまざまな手段やメリット・デメリットをはじめ、自社に最適なシステムの選び方をとことんお伝えします!
サクッと理解!本記事の要点まとめ
建設業でアナログな受発注業務を続けることの具体的なリスクは何ですか?
建設業で電話、FAX、Excelなどのアナログな受発注業務を続けることには、主に3つのリスクがあります。
1.生産性の低下とヒューマンエラー: 書類作成や転記作業に時間がかかるだけでなく、聞き間違いや入力ミスといった人為的ミスが発生しやすく、手戻りや工期遅延の原因となります。
2.属人化と機会損失: 担当者しか取引状況や価格を把握できない状況(属人化)に陥りやすく、担当者不在時に対応が遅れ、ビジネスチャンスを逃す可能性があります。
3.コストとコンプライアンス: 紙の印刷・郵送・保管にかかる物理的なコストに加え、インボイス制度など法改正への対応が煩雑になり、管理コストが増大します。
建設業向けの受発注システムを選ぶ際、クラウド(ASP)型ではなく、あえて自社専用の「BtoB ECサイト」を構築するメリットは何ですか?
クラウド(ASP)型は手軽ですが、機能のカスタマイズができません。一方、自社専用の「BtoB ECサイト」を構築する最大のメリットは、自社の複雑な商習慣に合わせた柔軟なカスタマイズが可能な点です。具体的には、以下のようなメリットがあります。
・取引先ごとの価格設定: 協力会社ごとの掛け率を自動で適用し、各社専用の価格を表示できます。
・独自の業務フローに対応: 複雑な見積もり機能や承認フローなど、自社独自のルールをシステムに反映できます。
・顧客満足度の向上: 24時間発注可能で、過去の履歴も簡単に参照できる利便性の高い窓口を提供することで、協力会社との関係性を強化し、顧客を囲い込むことができます。
建設業の受発注システム導入で失敗しないために、システム選定時に最も重要なチェックポイントは何ですか?
システム選定で失敗しないためには、4つのポイント(コスト、機能、セキュリティ、サポート)を総合的に見ることが重要ですが、特に重要なのは「自社の課題解決に直結する機能が過不足なく備わっているか」を見極めることです。多機能すぎても使いこなせずコストが無駄になりますし、必要な機能がなければ導入の意味がありません。まずは「絶対に譲れない機能」を明確にし、それが標準機能で対応できるのか、カスタマイズが必要なのかを判断することが失敗を防ぐ鍵となります。
なぜ今、建設業で受発注システムの導入が急務なのか?
多くの業界でデジタル化が進む中、なぜ今あらためて建設業で受発注システムの導入が重要視されているのでしょうか。その背景には、業界特有の構造的な課題と、外部環境の大きな変化があります。
課題1:深刻化する人手不足と働き方改革への対応
建設業界は、依然として深刻な人手不足に直面しています。その中で「働き方改革関連法」の適用により、長時間労働の是正は待ったなしの状況です。
限られた人員で生産性を維持・向上させるためには、電話応対や書類作成といった間接業務を徹底的に効率化し、本来注力すべき業務に時間を割ける環境を整える必要があります。
課題2:アナログ業務に潜むコストとリスク
電話、FAX、メール、Excelといったアナログな管理方法は、一見するとコストがかかっていないように見えます。しかし実際には、情報の聞き間違いや転記ミス、書類の紛失、担当者しか状況が分からない属人化といった多くのリスクを内包しています。これらの小さなミスや非効率の積み重ねが、結果的に工期の遅延や手戻りを発生させ、大きな損失に繋がるのです。
課題3:複雑な商習慣とサプライチェーン
建設業は、元請けから一次・二次下請けへと続く多重下請け構造や、現場ごとの資材調達など、サプライチェーンが非常に複雑です。
多くの協力会社とやり取りを行う上で、スムーズで正確な情報共有はプロジェクト成功の生命線と言えます。アナログな手法では、この複雑な情報伝達に限界がきているのが現状です。
受発注システム導入で得られる5つのメリット
では、受発注システムを導入することで、具体的にどのようなメリットが生まれるのでしょうか。
1. 業務の圧倒的な効率化と時間創出
見積書や発注書、請求書の作成・承認フローをシステム上で完結できます。過去の取引履歴からワンクリックで書類を作成したり、承認作業を電子化したりすることで、書類作成や待ち時間を大幅に削減します。
2. 人的ミスの撲滅と正確な情報共有
システムを介してやり取りがすべて記録されるため、「言った言わない」のトラブルを防ぎます。また、発注履歴や図面、仕様書といった関連情報も案件に紐づけて一元管理できるため、協力会社との認識齟齬をなくし、正確な情報共有を実現します。
3. ペーパーレス化によるコスト削減
紙での書類発行や郵送、保管が不要になるため、印刷代やインク代、郵送費、保管スペースといった目に見えるコストを直接的に削減できます。2023年10月から始まったインボイス制度への対応も、電子化によってスムーズになります。
4. 場所を選ばない業務体制の実現
クラウド型のシステムであれば、インターネット環境さえあれば、事務所だけでなく現場や出張先、自宅からでも受発注状況の確認や承認作業が可能になります。これにより、担当者の柔軟な働き方をサポートします。
5. データ活用による経営の可視化
システムに蓄積された受発注データを分析することで、「どの協力会社への発注が多いか」「どの資材の価格が変動しているか」といった経営判断に役立つ情報を可視化できます。どんぶり勘定から脱却し、データに基づいた戦略的な購買活動へと繋げられます。
建設業向け受発注システムの構築方法 比較表
受発注システムの導入を検討する際にはまず、自社の事業規模や目的に合う、システムの「構築方法」を検討することがとても大切です。
| 構築方法 | 事業規模(目安) | 初期費用 | 月額費用 | 拡張性(カスタマイズ) |
|---|---|---|---|---|
| 自社専用ECサイト構築 | 1億円〜 | 500万円〜 | 10万円〜 | ◎ 可能 |
| パッケージ | 1億円〜 | 500万円〜 | 10万円〜 | ○ 可能 |
| オープンソース | 5千万円〜5億円 | 0円〜 (構築費は別途) |
5万円〜 | ○ 可能 |
| クラウド(ASP) | 〜1億円 | 0円〜10万円 | 1万円〜10万円 | × 不可 |
それぞれの構築方法について、具体的にご紹介します。
機能が充実し、カスタマイズも可能な「パッケージ」
「パッケージ」とは、受発注管理に必要な機能を一通り揃えたシステムをベースに、自社の業務に合わせて機能を追加・改修していく構築方法です。
既に完成されたシステムを基盤とするため、ゼロから開発するよりもコストと時間を抑えつつ、自社の要望を反映させやすいのが特徴です。建設業界向けのパッケージであれば、業界特有の商習慣に対応した機能が予め備わっていることもあります。
ただし、独自の業務フローが非常に多い場合、カスタマイズ費用が高額になる可能性も考慮する必要があります。
低コストだがリスクも伴う「オープンソース」
「オープンソース」とは、プログラムの設計図(ソースコード)が一般公開されており、誰でも無償で利用できるソフトウェアを指します。
ライセンス費用がかからないため、開発知識があれば理論上は最も安価にシステムを構築できます。しかし、セキュリティ対策やシステム障害が発生した際の対応は、すべて自社の責任となります。近年、オープンソースの脆弱性を狙った情報漏洩事故も多発しており、導入には信頼できる開発パートナーと、継続的な保守運用体制が不可欠です。
手軽に始められるが、拡張性に乏しい「クラウド(ASP)」
「クラウド(ASP)」は、サービス提供事業者が用意したシステムを、インターネット経由で月額利用料を支払って利用する形態です。
サーバーの準備も不要で、初期費用を抑えてスピーディに導入できるのが最大のメリットです。しかし、提供されている機能の範囲でしか利用できず、自社独自の機能追加(カスタマイズ)は基本的にできません。そのため、「自社の業務をシステムに合わせる」という運用になりがちで、事業が拡大していく過程で機能的な限界を感じるケースも少なくありません。
【これからの新常識】自社専用の「BtoB ECサイト」という選択
ここまでの選択肢は、いわば既存の業務を「効率化」するためのものでした。しかし、これからの時代に求められるのは、単なる効率化に留まらない、ビジネスを成長させる「攻めのDX」です。その最も有効な手段が、自社専用の「BtoB 受発注ECサイト」を構築するという選択肢です。
ECサイトと聞くと、一般消費者向けの通販サイトを思い浮かべるかもしれませんが、企業間取引(BtoB)に特化したECサイトは、建設業の複雑な受発注業務を革新する大きな可能性を秘めています。
- 取引先ごとに価格や表示商品を変更可能
→ 協力会社ごとの取引条件(掛け率)をシステムに登録し、ログインするだけで各社専用の価格が自動で表示されるように設定できます。 - 複雑な見積もり依頼にもWebで対応
→ 図面や仕様書を添付して見積もりを依頼できるフォームや、オプション選択式の自動見積もり機能など、パッケージ製品では対応が難しい独自の要件も実現できます。 - 24時間365日、自動で注文受付
→ 担当者の不在時や休日でも注文を受け付けることができ、機会損失を防ぎます。これは協力会社にとっても大きな利便性向上に繋がります。 - 顧客の囲い込みと関係性強化
→ 「あの会社のサイトは発注が楽で助かる」という体験を提供することで、協力会社とのエンゲージメントを高め、安定した取引関係を構築します。
単にシステムを導入するだけでなく、自社独自の「オンライン受発注窓口」を持つことで、業務効率化はもちろん、取引先満足度の向上、そして新たなビジネスチャンスの創出へと繋げることができるのです。
システム選定で失敗しないための4つのチェックポイント
どの構築方法を選ぶにせよ、最終的なシステムを選定する際には、以下の4つのポイントを必ず確認しましょう。
1. コスト
初期費用だけでなく、月額費用やカスタマイズ費用、保守費用など、長期的な視点でのトータルコストを比較検討することが重要です。特に、売上やデータ量に応じて費用が変動する料金体系の場合は、将来的な事業拡大を見据えたシミュレーションが不可欠です。
2. 機能の過不足
多機能すぎても使いこなせなければ意味がありませんし、機能が不足していては導入の目的を達成できません。まずは「絶対に譲れない機能(Must)」と「あると嬉しい機能(Want)」を洗い出し、自社の課題を解決できるかを冷静に見極めましょう。
3. セキュリティ
取引先の重要な情報や取引データを扱う以上、セキュリティ対策は最重要項目です。システムの脆弱性対策はもちろん、データセンターの安全性や、サービス提供企業のプライバシーマーク取得状況なども確認し、信頼できるサービスを選定しましょう。
4. サポート体制
システムの導入時だけでなく、運用開始後にトラブルが発生した際や、操作方法に不明点があった際に、迅速かつ的確なサポートを受けられるかは非常に重要です。サポートの対応時間や連絡手段、過去の実績などを確認し、安心して長く付き合えるパートナーを選びましょう。
まとめ:未来を切り拓く「攻めのDX」へ
ここまでお読みいただきありがとうございます。
建設業における受発注業務のデジタル化は、もはや単なる「守りの効率化」ではありません。
人手不足や法改正といった外部環境の変化に対応し、企業の競争力を高めていくための「攻めの経営戦略」と言えます。
数ある選択肢の中でも、自社の商習慣に完全にフィットさせ、協力会社との関係性を強化し、将来的な事業拡大にも柔軟に対応できる「自社専用のBtoB ECサイト構築」は、これからの建設業界を勝ち抜くための最もパワフルな一手となるでしょう。
まずは、自社の業務プロセスを改めて見直し、どこに課題があり、システムによって何を実現したいのかを明確にすることから始めてみてはいかがでしょうか。
御社のビジネスを加速させる、最適なECサイト構築をご提案します。
弊社では、1600サイト以上の導入実績を誇るノウハウを活かし、建設業界の複雑な商習慣にも対応可能なBtoB ECサイトの構築をサポートしております。
「何から始めたら良いかわからない」「自社の場合はどんなことができるのか知りたい」といった初期段階のご相談からでも大歓迎です。ぜひお気軽にお問い合わせください。