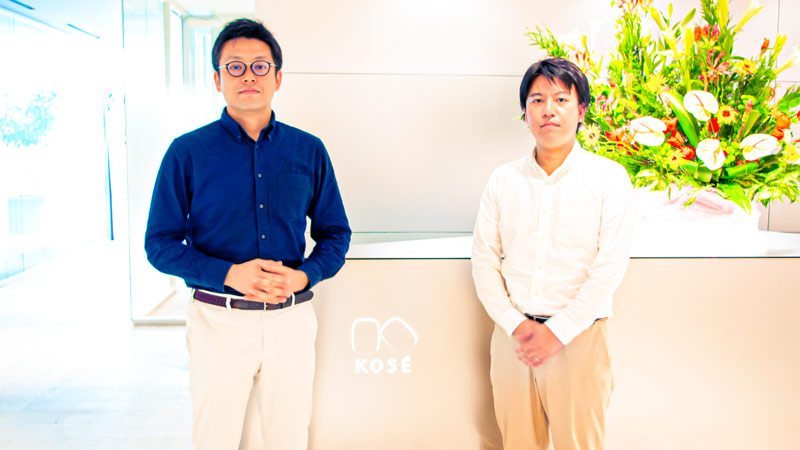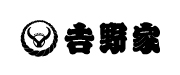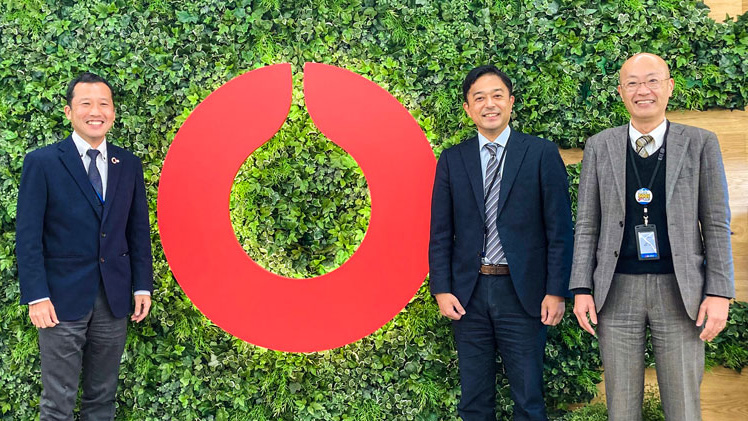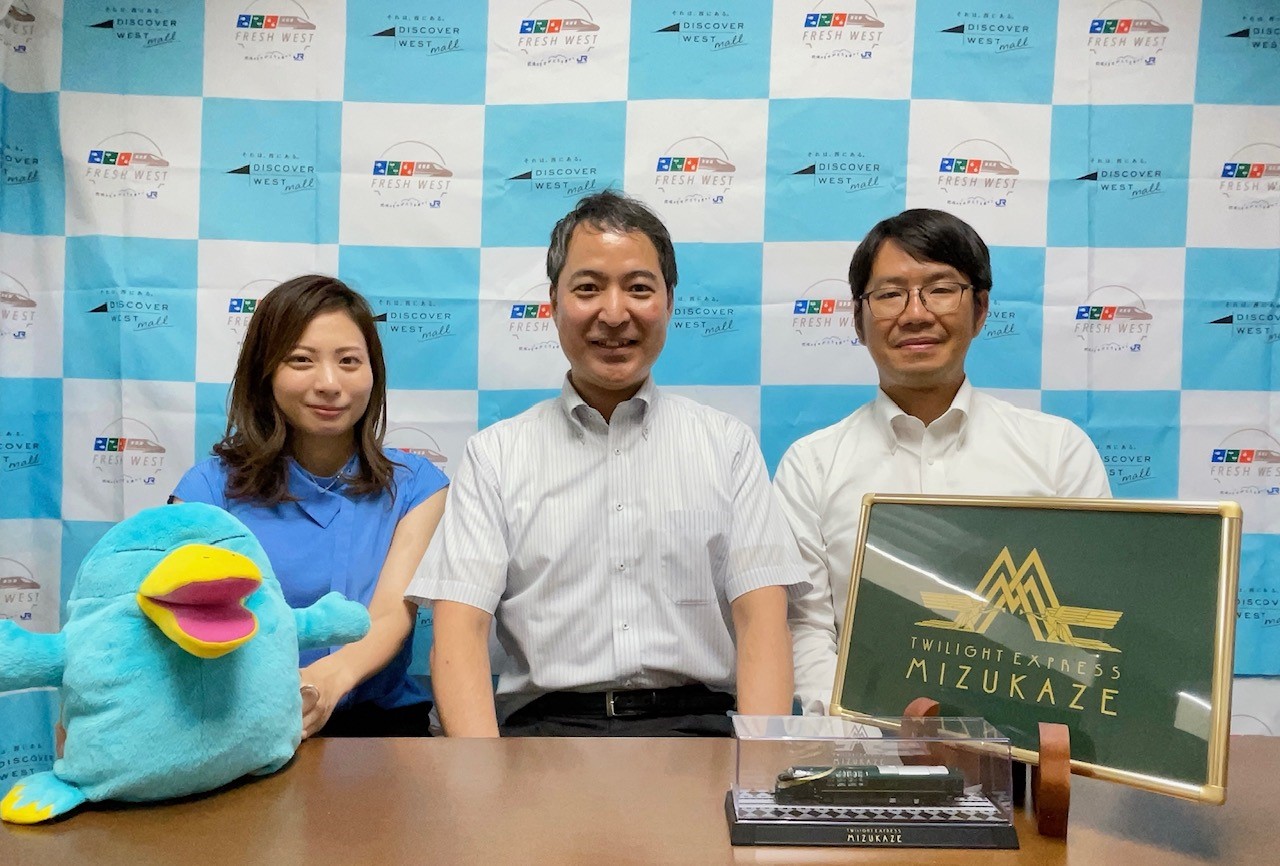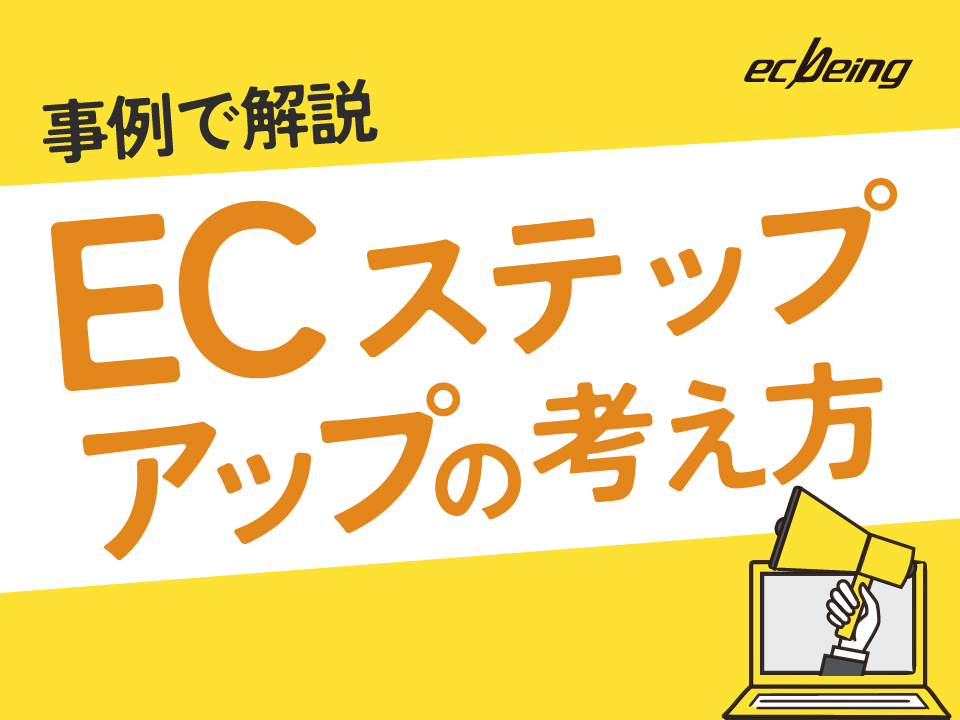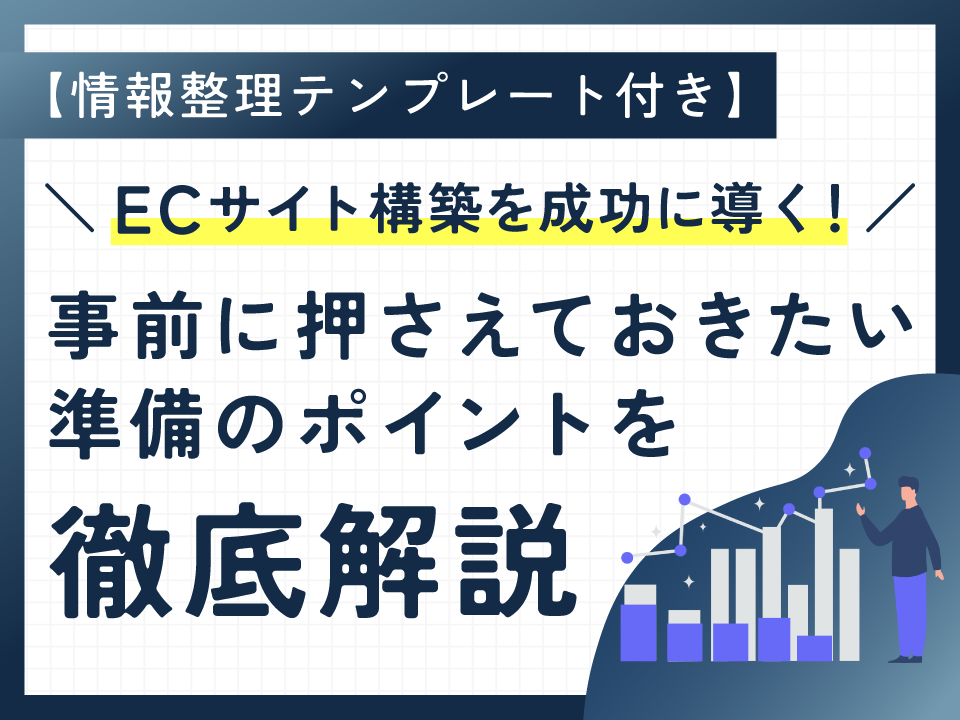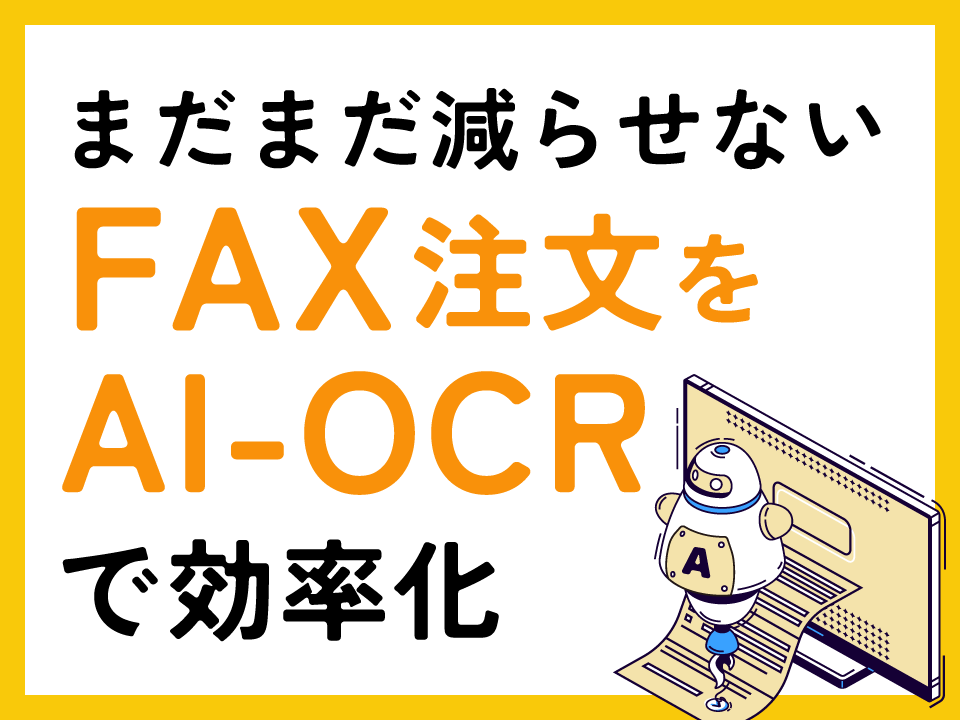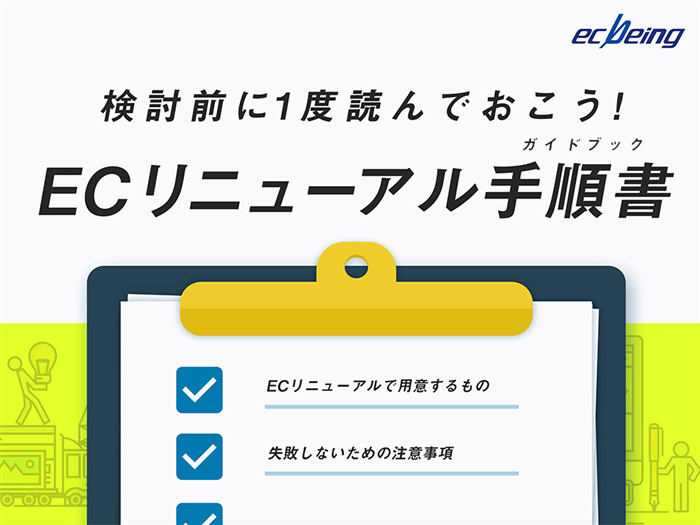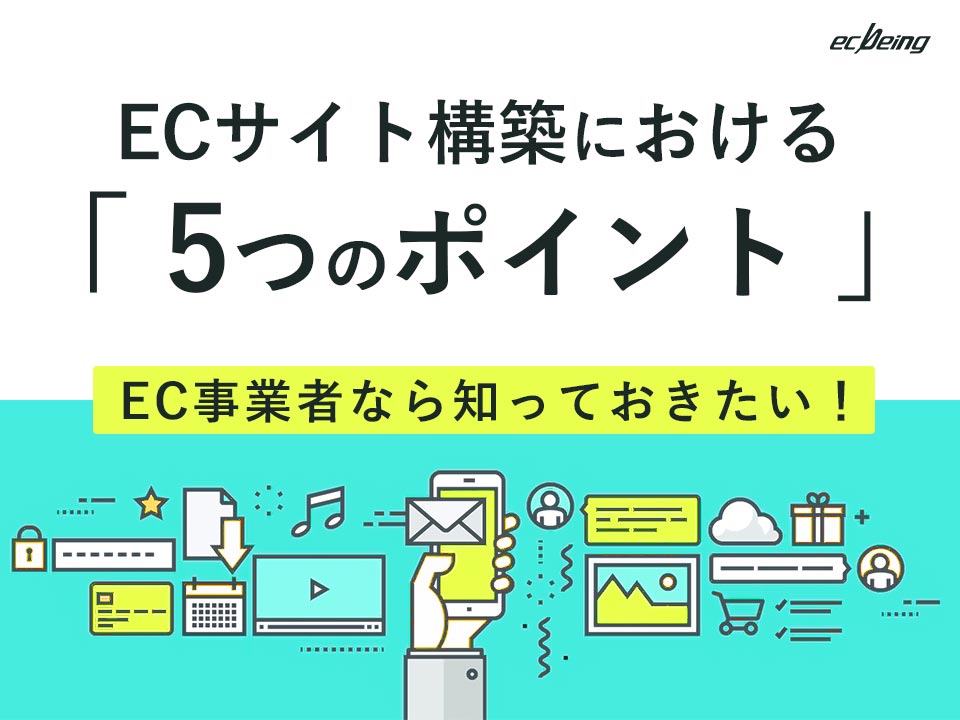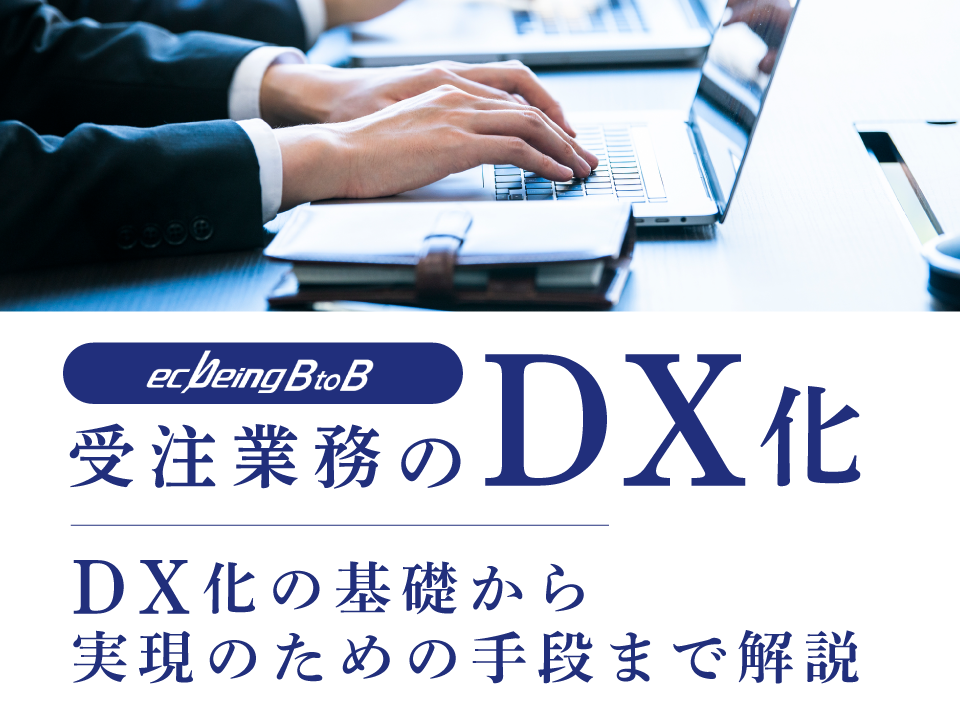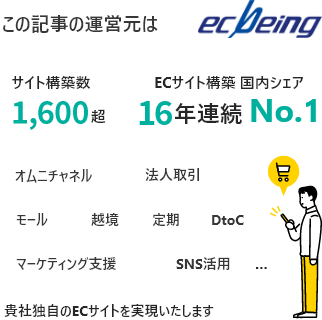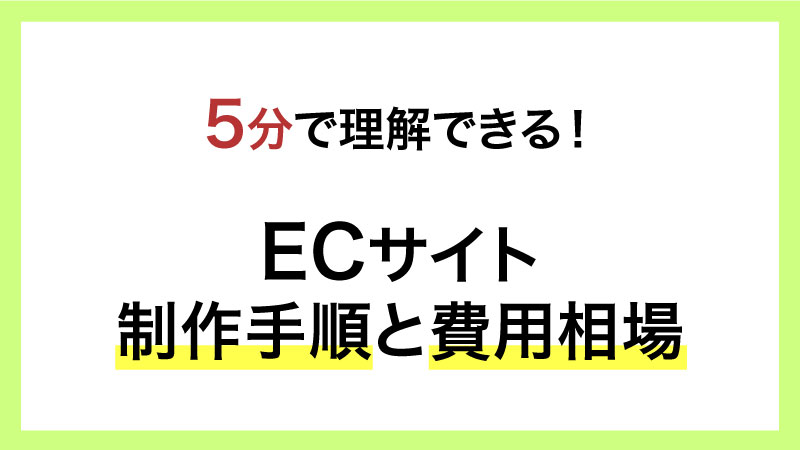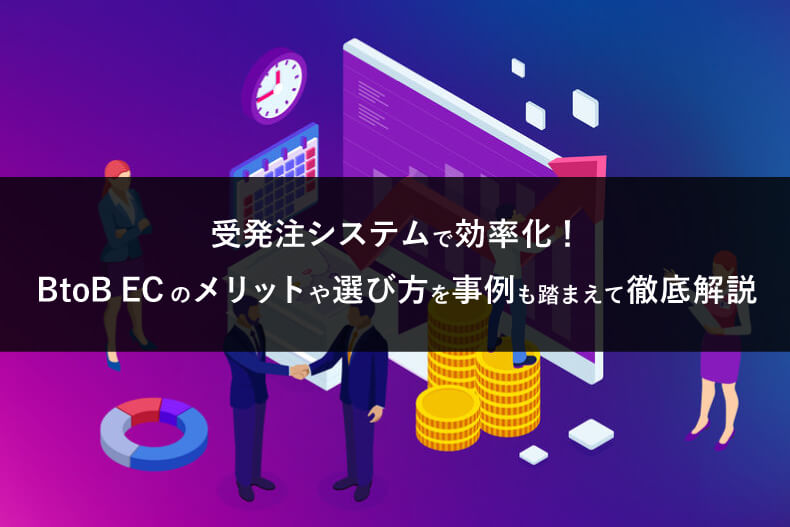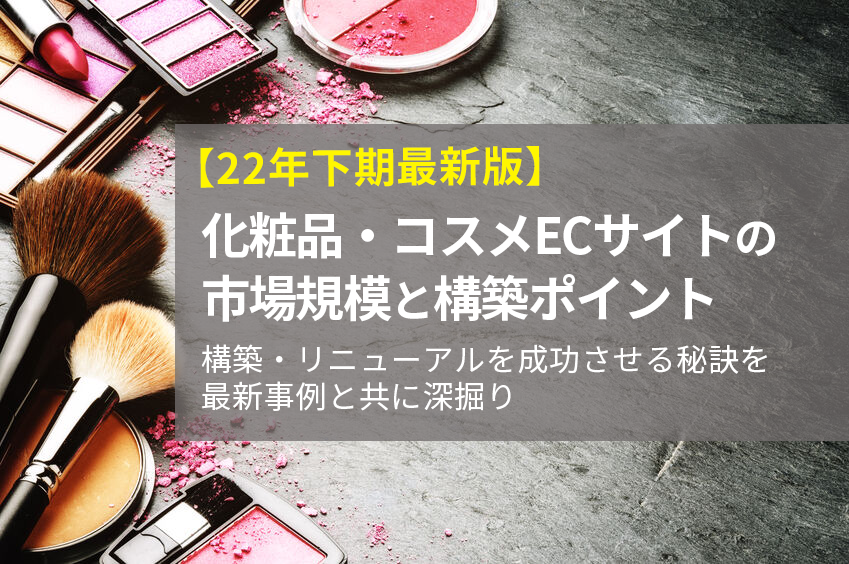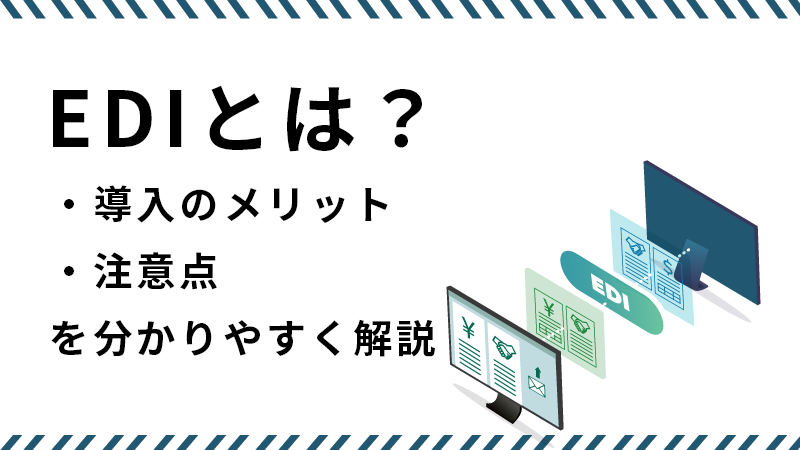マルコメがBtoCとBtoB、2つのECサイトをecbeingで構築。BtoCではEC化率が5%から25%に。

2006年に通販専用のフリーズドライお味噌汁「京懐石」を販売するためにECサイトを自社開発でオープンしているマルコメ。その後、ecbeingのパッケージを利用して、2015年と18年に2度のリニューアル、さらにBtoBサイトを18年に新規オープンしている。
なぜ、マルコメはパートナーにecbeingを選んだのか? マルコメ株式会社の大原直木さんに話を聞く。
マルコメ 基本情報

<社 名>
マルコメ株式会社
<設立年月日>
1854年(安政元年)
<事業内容>
家庭用・業務用みそ・即席みそ汁の製造販売/家庭用・業務用糀食品の製造販売/家庭用・業務用大豆関連食品の製造販売/家庭用・業務用発酵製品、及びそれに関わる機器等の販売/スープ等原料の製造販売(ラーメンチェーン等)/加工用みその製造販売(対食品メーカー向け)/海外向け商品の開発
<従業員数>
436名(男349名・女87名)
<資本金>
1億円
<所在地>
長野県長野市安茂里883番地
味噌だけでなく、甘酒や大豆製品も販売
――マルコメさんはBtoBとBtoCの2つのECを運営されていますが、それぞれのサイトで販売している商品について教えてください。
BtoCのほうは2006年頃に「マルコメの味噌をはじめとした発酵食品をどこでも手軽に買えるようにしたい」という思いのもとオープンしています。当初は通販限定のフリーズドライのお味噌汁「京懐石」をメインで販売していましたが、最近は味噌に限らず、「糀甘酒」や「大豆のお肉シリーズ」「大豆粉シリーズ」などの大豆製品も販売していて、全部で50品ほどのラインナップがあります。
BtoBサイトは2018年10月に新規オープンしましたが、まだ本格稼働はしていません。以前は問屋から商品を仕入れる飲食店が一般的でしたが、現在は問屋から商品を仕入れない新たな業態が出てきているので、そこに対しても弊社の商品を卸すことができるようにしたいと思ってつくっています。そのため、こちらはケース単位であれば、どの商品でも購入できる仕様にしています。
ecbeingを選んだのは、コスト面、スピーディな対応、デジタル施策
――BtoCサイトは2006年頃にオープンされたということですが、現在までにどのように運営やリニューアルをされてきたのでしょうか?
BtoCサイトは当時、自社のフルスクラッチで制作しました。この頃はお客様の大半を年齢層が上の方が占めていたため、注文の85%が電話、ネット注文は5%程度だったので、これでも十分に対応することが可能だったんですね。
そのサイトはスマホが登場する前につくったものなのでスマホに対応していなかったり、クレジットカードのセキュリティの改修にも手間がかかったりと、時代の流れに合わなくなってきている部分がありました。自社開発で常に変化する技術に対応するのは難しいと判断したため、2015年3月にecbeingに依頼して、ほぼ新設する形でリニューアルを行っています。さらに、2018年7月にも2度目のリニューアルをしています。
――なぜecbeingをパートナーに選んだのでしょうか?
ecbeingさんと初めて会ったのは2014年に行われた「Japan IT Week」でした。そのときに「ECのリニューアルを考えている」と話したところ、すぐに会社に来てくれて、そこでうちの要望をいろいろと伝えました。
ecbeingともう1社に相談したのですが、コスト面に優位性があったこと、担当の方がとてもスピーディに対応してくれたこと、また、実施したいと思っていたメルマガやクーポンなどのデジタル施策もecbeingのパッケージを使えば簡単にできそうなことなどが決め手になり、ecbeingさんに依頼することにしたんです。
――1度目のリニューアルは「スマホ対応など時代に合ったECをつくる」ことが背景にあったということですが、2018年7月の2度目のリニューアルは?
2度目のリニューアルは「コーポレートサイトと揃える」ことが目的でした。以前はコーポレートサイトとデザインが異なっていましたが、同じマルコメが運営しているサイトなので同じ見え方にしたほうがいいと思ったんです。ECサイトは商品販売だけでなく、その食材を使ったレシピなどのコンテンツもあり、それをコーポレートサイトと共有しているため、途中で明らかにデザインが変わると違和感がありますよね。
また、以前はコーポレートサイトとECサイト、それぞれ会員情報を管理していましたが、ECサイトのほうで統一して管理できる仕様にも変更しました。
BtoCの中に間借りしていたBtoBを独立させる
――BtoBサイトについても教えてください。2018年10月に新規オープンした背景には何があったのでしょうか?
実はBtoBも2015年にecbeingさんにつくっていただいたBtoCサイトの中にあったんです。簡単に言うと、ログイン情報が「個人か」「法人か」によって、表示する中のコンテンツだけを分けていたんですね。
ただ、ログイン情報のメールアドレス1つに対して1個のIDしか与えることができないため、BtoBのサイトで買うお客様はBtoCのほうでは買えない仕様になっていました。こちらとしては両方で買ってもらいたいので、それは改善したいなと。
また、法人の場合は個人と違って会員登録に簡単な審査の段階があるため、使おうと思ってから実際に使いはじめるまでにどうしてもタイムラグが生まれていました。そこもリニューアル後のBtoBサイトでは、弊社の営業から直接案内したお客様はタイムラグなく、すぐに使える仕様にしたいと思っていました。
――先ほど、BtoBは「まだ本格稼働してない」ということでしたが、いつ頃から本格的にオープンする予定ですか?
ほとんど中身はできているんですが、社内の準備とお客様への案内ができていないだけなので、5月の連休明け頃からは正式に使えるようになる予定です。
苦労して開発した「お好みセット」が最も多い購入法に
――開発に関するお話も聞かせてください。BtoC、BtoB、それぞれで開発段階の苦労があったと思うのですが、まずはBtoCのほうはいかがでしたか?
弊社のお客様は電話注文の方が以前と変わらずに多いため、1回目のリニューアルのときはECで快適に買い物ができるだけでなく、「電話注文にも対応できるシステム」の構築を依頼しました。そこは大変だったと思います。具体的には社内の人間が使う管理画面を工夫してもらって、電話注文を受けたときに管理コードを入れれば商品名が出るなど、スムーズかつ間違いの起こらないシステムをつくってもらったんです。
お客様が使うシステムでは、「定期購入」と「お好みセット」の2つの機能に力を入れてつくっています。お好みセットは、好きな商品を組み合わせて、好きな数だけカートに入れることができて、その数が増えるほどボリュームディスカウントがされて、さらに定期購入にすると割引されるという複雑な仕様です。開発にはとても苦労されたと思います。
完成した「お好みセット」の機能は評判がよくて、現在、BtoCサイトの中で最も購入者が多い購入法になってますね。
――BtoBのほうの苦労したポイントは?
これは現在進行形の話ですが、今はまだ注文内容をエクセルに入れて、請求書をつくり、発送するという流れを手作業でやっています。ここが自動化されると私たちの業務がかなり効率化されるので、そこはまさに今、ecbeingさんと相談しながら進めているところです。
EC化率は5%から25%に変化
――完成後の反応や社内の業務の変化は、どのようなものがありますか?
2015年にリニューアルしたBtoCサイトは、社内の運用面がかなり効率化されました。以前は受注データをECのデータとマスターと両方に登録しなければなりませんでしたが、それを1つにまとめられたので業務の負担は軽くなりましたね。また、以前のECは後払いの振り込みだったので、自分たちで入金確認や督促をする必要がありましたが、今はそれもなくなったこともあり、EC関連のスタッフは5人から3人で回せるようになっています。
他にも、EC化率が5%程度だったところから約25%にまで上がりました。これはECが使いやすくなったことがメインの要因ですが、加えて、糀甘酒を販売して若者層を取り込んだことも大きく影響しています。今は京懐石や味噌よりも糀甘酒のほうがよく売れていて、全体の購入比の2割を占めるほどに成長しています。
――今後、ecbeingのこの機能を使ってみたいというものはありますか?
visumoとAmazon Payですね。すでにメルマガキャンペーンやクーポン配布は簡単に使うことができたので実施済みで、これからも使っていく予定です。私たちはアナログ派で、変わらずにチラシなどの紙の広告も使っていきますが、ECで購入してもらったほうが業務も効率化できるので、どんどんECに誘導していきたいと思っています。
EC開発で大切なのは「バランス」。それを見極めるためにecbeingに全て話す
――それぞれのサイトの目標値や今後の展望を教えてください。
BtoCのほうは全体のお客様数を増やしていきながら、EC化率を40%ぐらいまで引き上げたいですね。現状の電話注文の数を減らしてEC化率を上げるのではなく、全体の底上げをしながらEC化率を上げていきたいと考えています。
あとは糀甘酒が若者にうけているので、購入比率をこちらも40%程度まで伸ばせればと思っています。糀甘酒を販売してから定期購入利用が800件から2,500件までに増えています。さらに伸ばすためにはスーパーと同じように買えるだけでなく、EC限定品や定期購入者に対するメリットを考える必要があると思っています。
BtoBはEC化率が2%程度なので、10%ぐらいまで伸ばしたいですね。まずは本格稼働できるように、しっかり準備を進めたいと思います。
――ありがとうございました。最後に、これからEC事業をはじめる企業や、うまくいかなくて困っている企業に向けてアドバイスをお願いします。
ECを新規で立ち上げようとすると、それなりのコストがかかるため、しっかりと売れる見込みが立つ商品が必要です。うちの場合はそれがフリーズドライの京懐石でしたが、このようにEC限定の商品をつくっておくとよいと思います。
あとはECで全てを完結しようとすると、そのコストの高さに二の足を踏んでしまうでしょう。全てをECで行うのではなく、最初は社内の人間で対応が可能なところは除くなど、バランスを考えて開発していく方法がおすすめです。
そういうところもecbeingさんに相談すると、さまざまな提案をしてもらえるので、やりたいこと、考えてることは素直に全部話してしまうとよいと思います。
――
マルコメ株式会社
大原 直木(オオハラ ナオキ)
●取材・文:廣田喜昭

株式会社ecbeing
 03-3486-2631
03-3486-2631- 営業時間 9:00〜19:00