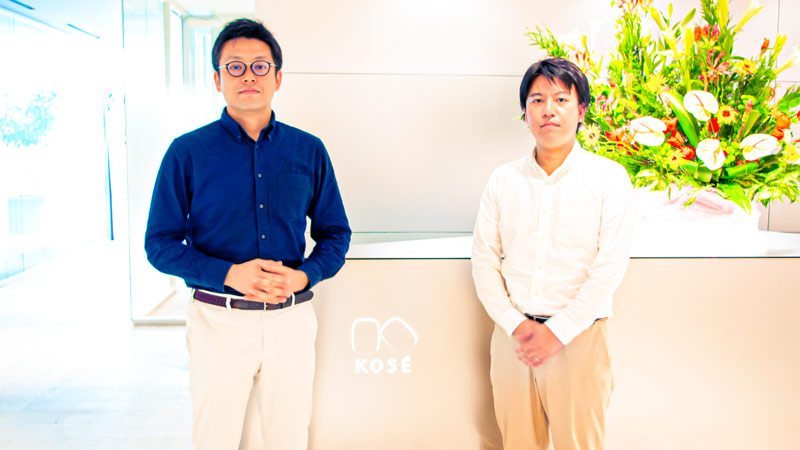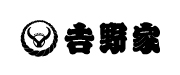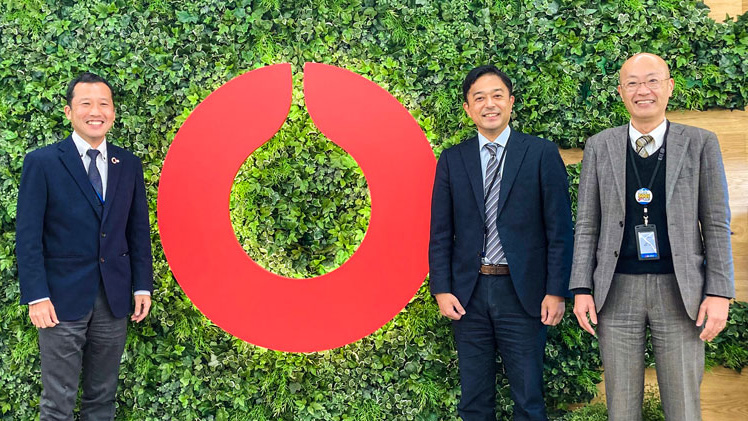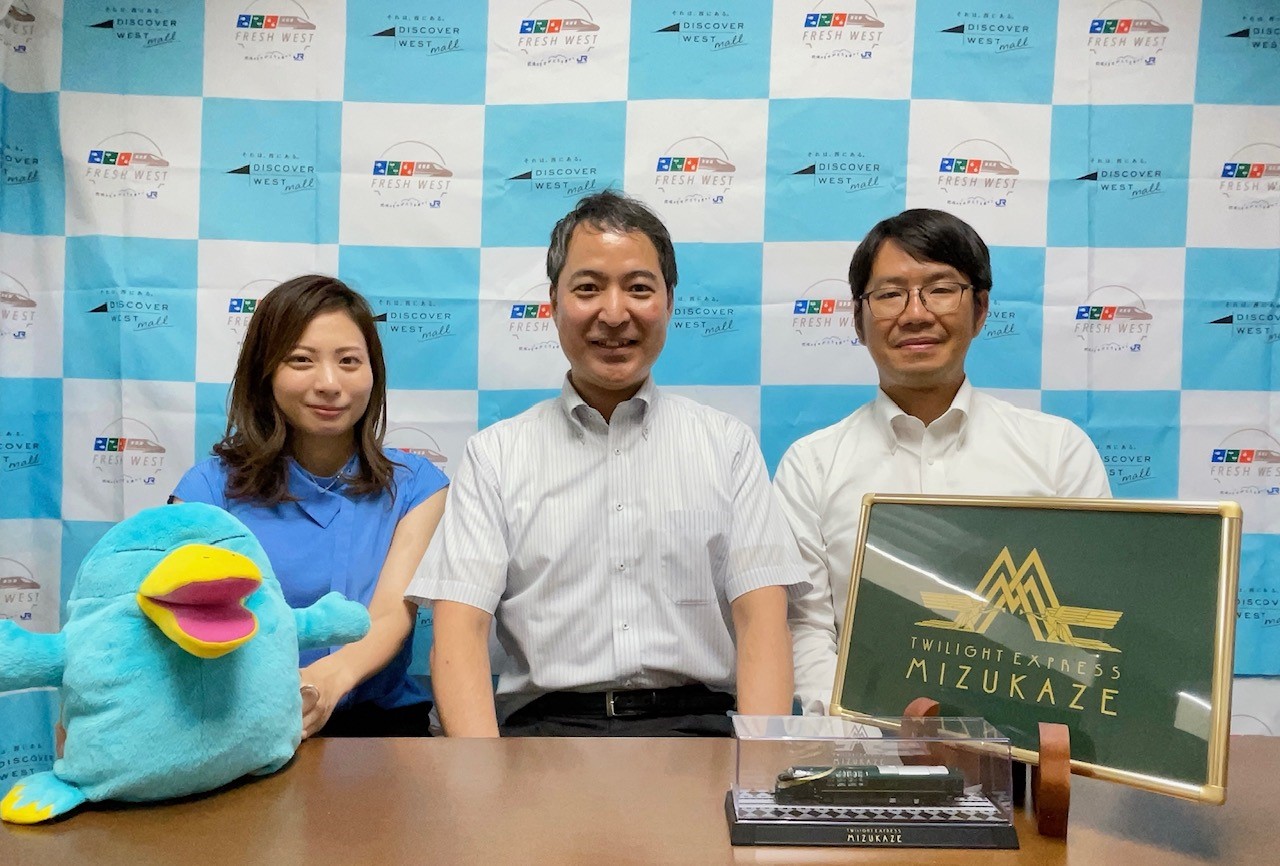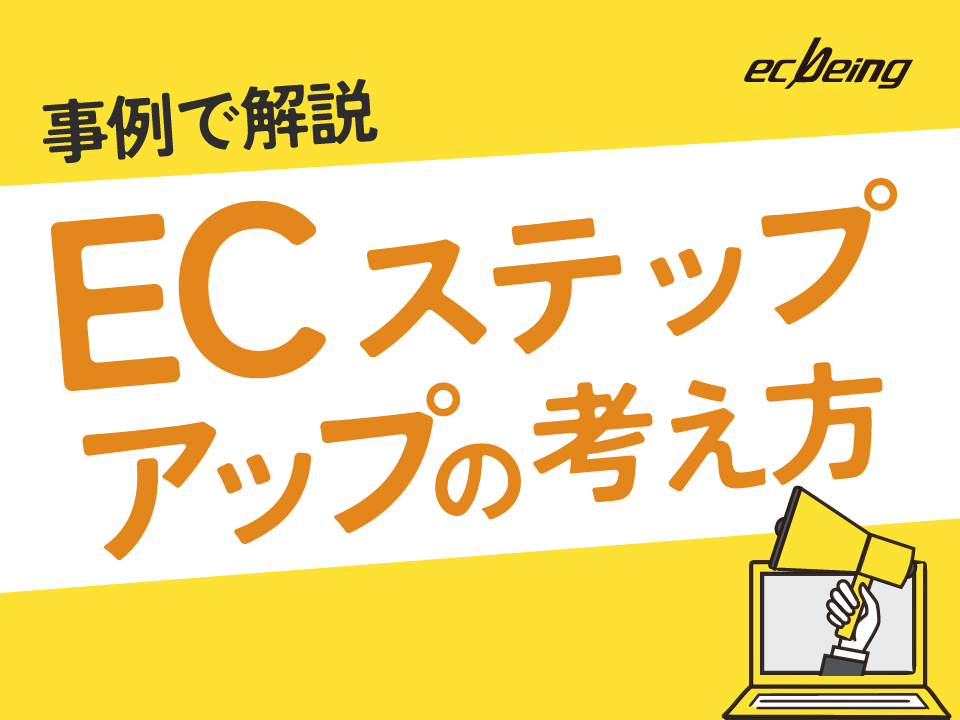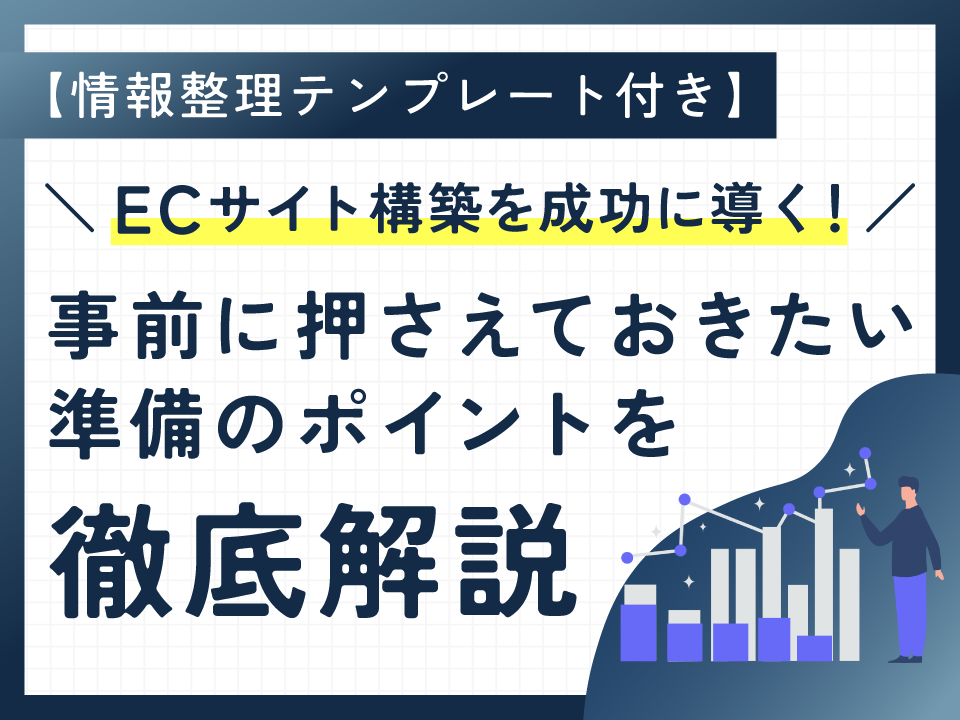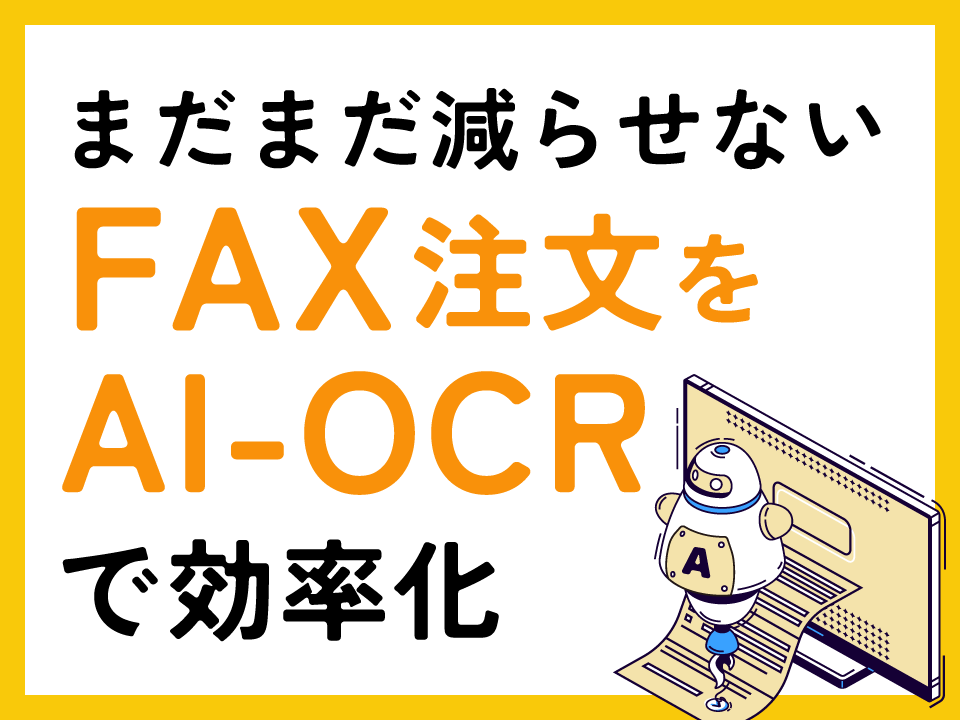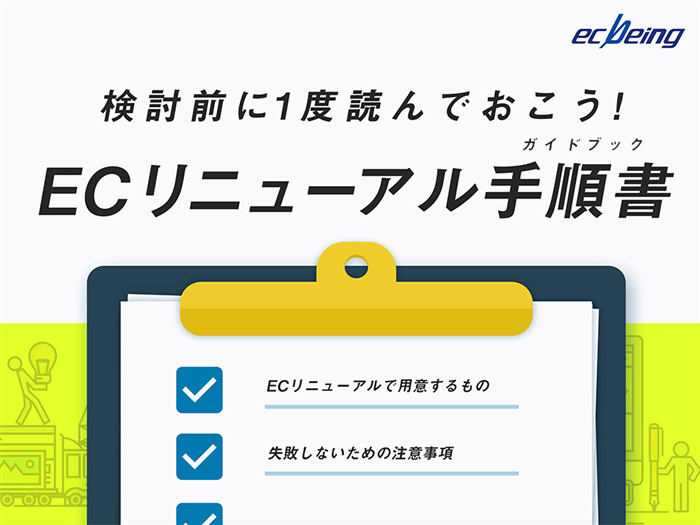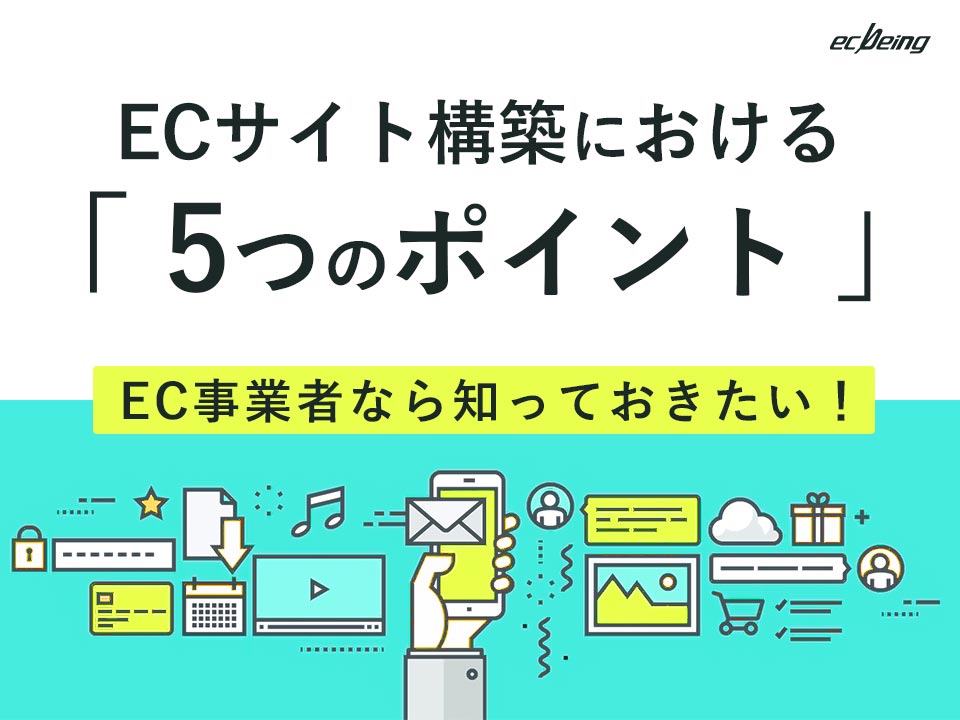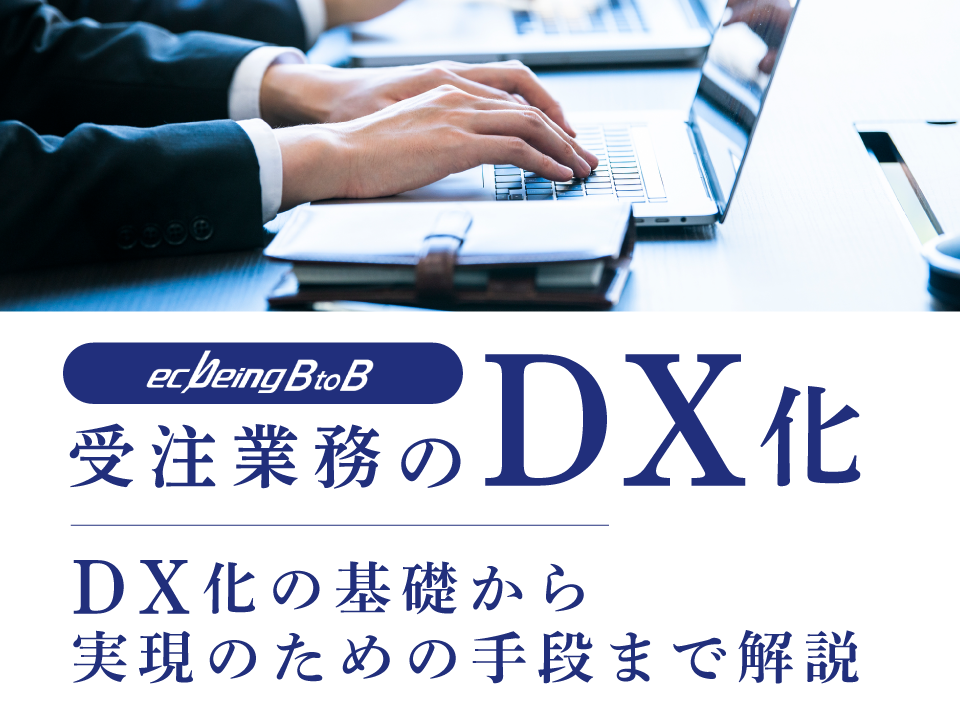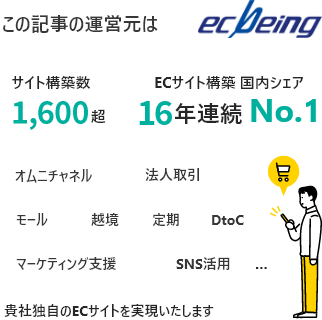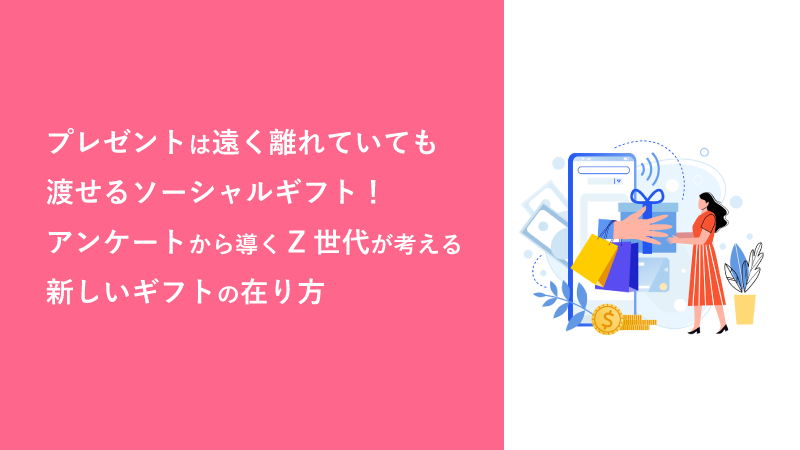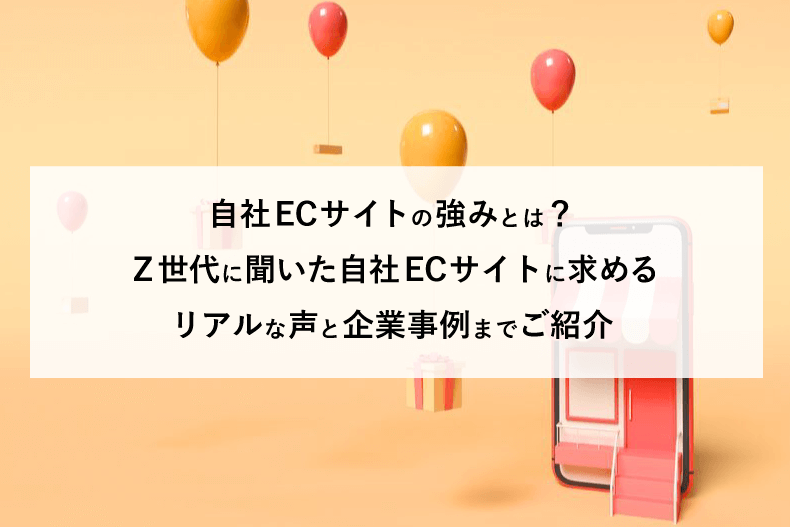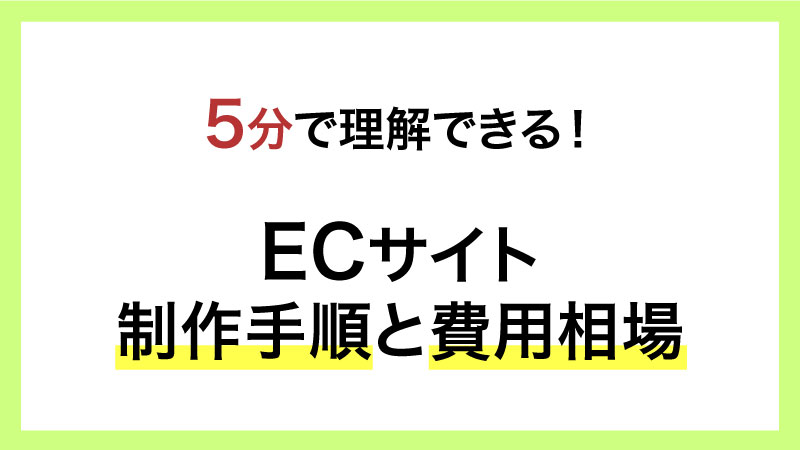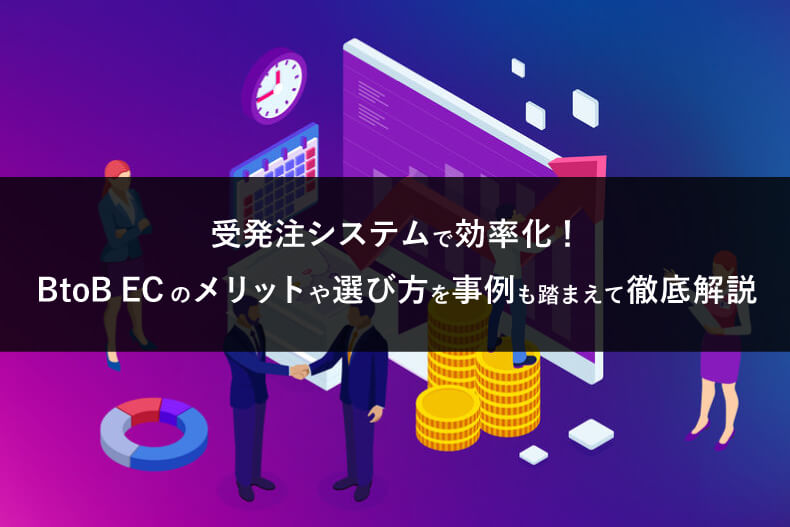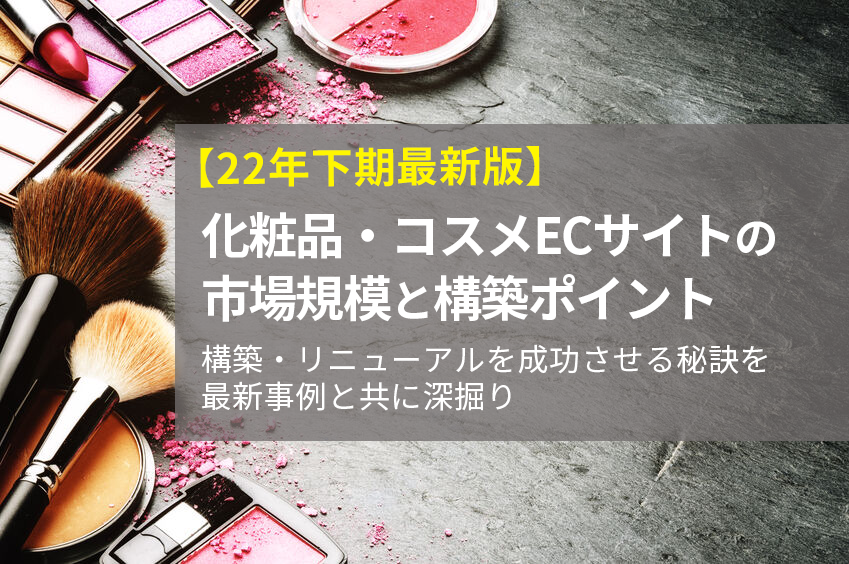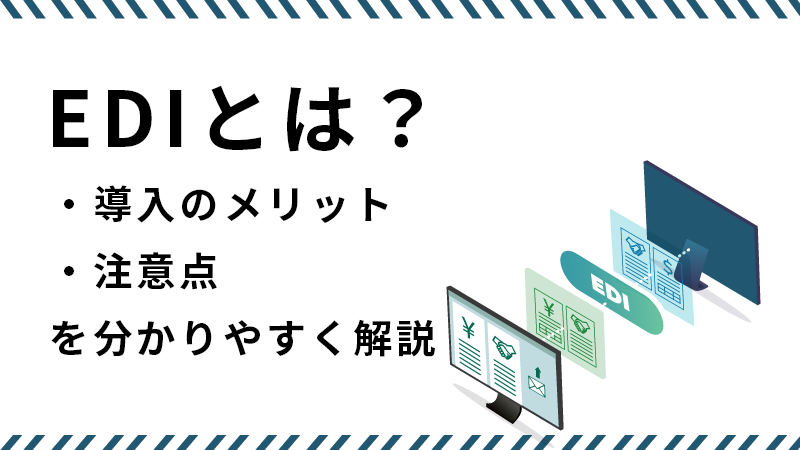いまさら聞けない「電子商取引」とは?EC・ネットショップとの違いから、その始め方までを徹底解説
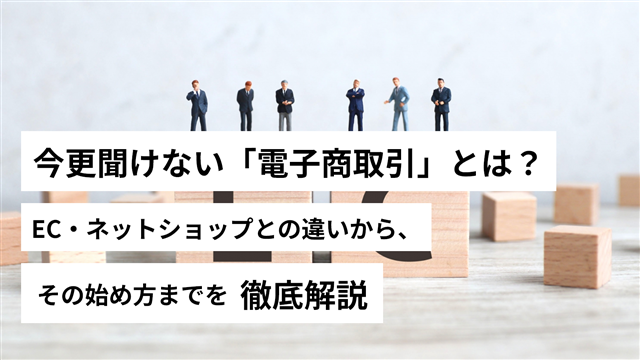
Webマーケティングや新規事業の立ち上げにおいて耳にする機会の多い『電子商取引』ですが、ECやネットショップといった類似する言葉も多く、その違いを明確に説明できる人はそう多くないのではないでしょうか。 市場には様々な情報が溢れ、言葉の解釈も文脈によってまちまちであることが、理解を難しくしている一因かもしれません。 そこで今回は、ビジネスのデジタル化において必須の知識である『電子商取引』について、その基本的な意味や市場の動向に立ち返って正しく理解し、これから事業を始めるための第一歩について解説します。
サクッと理解!本記事の要点まとめ
「電子商取引」「EC」「ネットショップ」は何が違うのですか?
「電子商取引」はインターネットや専用回線などを使った商取引全般を指す最も広い言葉です。「EC」はその英語略ですが、一般的にはインターネット上の商取引、特に「ネットショップ」事業を指して使われます。「ネットショップ」は、インターネット上で商品を売買するための具体的なWebサイトのことです。
電子商取引には、どのような種類がありますか?
取引の相手によって主に3種類に分けられます。企業が他の企業に販売する「BtoB」、企業が一般消費者に販売する「BtoC」(Amazonや楽天など)、そして個人が個人に販売する「CtoC」(フリマアプリなど)があります。
なぜ今、電子商取引(ECサイト)を始めることが重要なのでしょうか?
事業開始時は低コストで販売実績を積むためにECモールがおすすめです。成長期には自社ECサイトを構築し、ブランド力と顧客関係を強化します。成熟期には両方を活用したオムニチャネル戦略が効果的です。
ネットショップ(ECサイト)を始めたいのですが、どんな方法がありますか?
主に、Amazonや楽天市場に出店する「モール型」、手軽に始められる「ASPカート」、自由に構築できる「オープンソース型」、カスタマイズ性と安定性を両立した「パッケージ型」、ゼロから開発する「フルスクラッチ型」などがあります。事業の規模や予算に合わせて選ぶことが重要です。
初めてネットショップを開設する場合、どの方法がおすすめですか?
これからECサイトを始める方には、初期費用を抑え、比較的スピーディーに開店できる「ASPカート」が最も人気でおすすめです。専門知識があまりなくても、ECサイトに必要な機能一式をレンタルする形で利用できます。
「電子商取引」「EC」「ネットショップ」の違い
『電子商取引』と『EC』、『ネットショップ』は、同じような場面で使われがちですが、それぞれが指す範囲やニュアンスに違いがあります。まずは、これらの言葉の定義を整理してみましょう。
電子商取引とは?
電子商取引とは、その名の通り「電子的な手段を用いて行われる商取引」全般を指す言葉です。ここでの「電子的」とは、インターネットだけでなく、企業間の専用回線(EDIなど)を利用したデータのやり取りも含まれます。非常に広い範囲をカバーする言葉といえるでしょう。
ECとは?
ECは「Electronic Commerce」の略で、日本語に訳すと「電子商取引」となります。つまり、言葉の意味としては電子商取引とイコールです。「eコマース」とも呼ばれます。 ただし、実際の会話やビジネスの現場では、後述する「ネットショップ」や「ネットショップ事業」そのものを指して「EC」と呼ぶことが一般的になっています。
ネットショップとは?
ネットショップとは、インターネット上に構築された、商品を販売するためのWebサイトのことです。「オンラインショップ」や「ECサイト」とも呼ばれます。これは、数ある電子商取引の中でも、特に一般消費者が最も頻繁に利用する形態の一つです。
言葉のニュアンスと使われ方
まとめると、「電子商取引」という大きな枠組みの中に「EC」があり、その代表的な具体例として「ネットショップ」が存在する、と理解すると分かりやすいでしょう。 ただし前述の通り、ビジネスシーンでは「EC事業を始める」と言う場合、その多くは「ネットショップを開設・運営する」ことを意味します。この背景には、ネットショップ市場の急速な拡大が影響しています。 経済産業省の調査によると、2023年の日本国内のBtoC(消費者向け)のEC市場規模は24.8兆円に達し、年々成長を続けています。このことからも、いかにネットショップがビジネスにおいて重要な存在になっているかがわかります。
電子商取引の主な種類
電子商取引は、取引を行う当事者の関係性によって、主に3つの種類に分類されます。ご自身のビジネスがどれに当てはまるのかを考える上で、非常に重要な分類です。
BtoB (Business to Business)
企業が、他の企業に対して商品やサービスを提供する取引形態です。例えば、部品メーカーが自動車メーカーに部品を販売するケースなどがこれにあたります。一度の取引額が大きくなる傾向があり、継続的な取引が中心となります。
BtoC (Business to Consumer)
企業が、一般の消費者に対して商品やサービスを提供する、最も一般的な取引形態です。私たちが普段利用するAmazonや楽天といったネットショップは、このBtoCの代表例です。不特定多数の顧客がターゲットとなります。
CtoC (Consumer to Consumer)
個人が、他の個人に対して商品などを売買する取引形態です。メルカリのようなフリマアプリや、ネットオークションなどがこれに該当します。近年、スマートフォンの普及とともに急成長している市場です。
なぜ今、電子商取引(ECサイト)が重要なのか?
市場が拡大しているだけでなく、電子商取引、特にECサイトの運営には、売り手側にとって多くのメリットが存在します。
メリット1:商圏が全国、そして世界へ広がる
実店舗の場合、商圏は店舗周辺の地域に限られてしまいます。しかし、ECサイトならインターネットに繋がる環境さえあれば、日本全国、さらには世界中の人々が顧客になり得ます。これまでアプローチできなかった層にまで、自社の商品やサービスを届けるチャンスが生まれるのです。
メリット2:24時間365日、販売の機会を逃さない
ECサイトは、あなたが寝ている間も、休日も、自動で商品を販売し続けてくれる優秀な営業担当です。顧客は自分の好きなタイミングで買い物を楽しめるため、販売機会の損失を最小限に抑えることができます。
メリット3:コストを抑えてビジネスを開始・運営できる
実店舗を構えるとなると、土地や建物の賃料、内装費、人件費など、多額の初期投資や運営コストがかかります。一方、ECサイトであれば、これらのコストを大幅に削減できます。特に近年では、低コストで手軽に始められるサービスも増えており、スモールスタートでビジネスを始めたい方にとって大きなメリットとなります。
成功する電子商取引の始め方
では、実際に電子商取引、特にビジネスの可能性を大きく広げるECサイトを始めるには、どうすればよいのでしょうか。ECサイトの構築方法は多岐にわたりますが、自社の事業規模や目的、予算に合わせて最適なものを選ぶことが成功への鍵となります。 ECサイトの構築には、主に以下のような種類があります。
モール型
Amazonや楽天市場のような、既存のオンラインショッピングモールに出店する方法です。集客力がある反面、デザインの自由度が低く、手数料が発生します。
ASPカート(クラウド型)
ECサイトに必要な機能一式を、インターネット経由でレンタルするサービスです。初期費用を抑え、比較的スピーディーに開店できるため、初めてECサイトを構築する方に最も人気のある方法です。
オープンソース型
無償で公開されているソフトウェアを利用して、自由にECサイトを構築する方法です。カスタマイズ性が高い反面、専門的な知識やセキュリティ対策が必須となります。
パッケージ型
ECサイト構築用のソフトウェアを購入し、自社サーバーにインストールして構築する方法です。ASPとオープンソースの中間的な位置づけで、カスタマイズ性と安定性のバランスが取れています。
フルスクラッチ型
何もないゼロの状態から、完全にオリジナルのECサイトを開発する方法です。最も自由度が高いですが、開発期間もコストも膨大になります。
このように、ECサイトの構築方法にはそれぞれ特徴があります。 「どの方法が自社に合っているのかわからない」「失敗せずにECビジネスをスタートさせたい」とお考えの方は、ぜひ一度、専門家にご相談ください。 弊社では、お客様のビジネスプランやご予算に合わせた最適なECサイト構築のご提案から、開店後の集客サポートまで、ワンストップで支援いたします。まずはお気軽にお問い合わせいただき、あなたのビジネスの可能性を一緒に広げていきましょう。

株式会社ecbeing
 03-3486-2631
03-3486-2631- 営業時間 9:00〜19:00