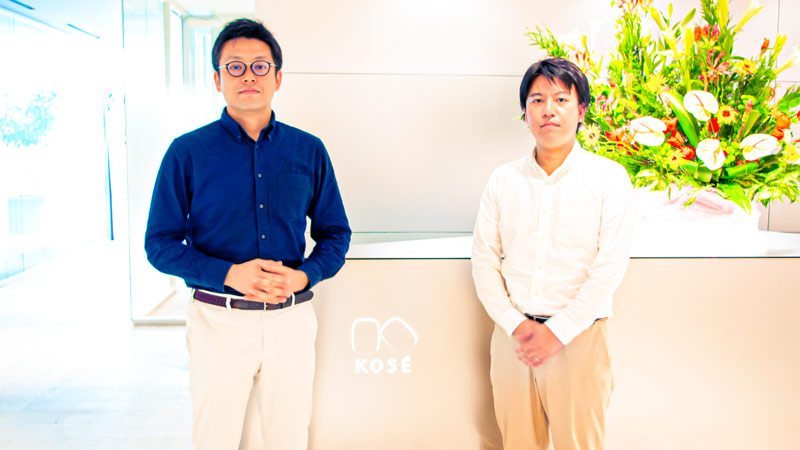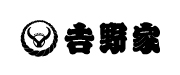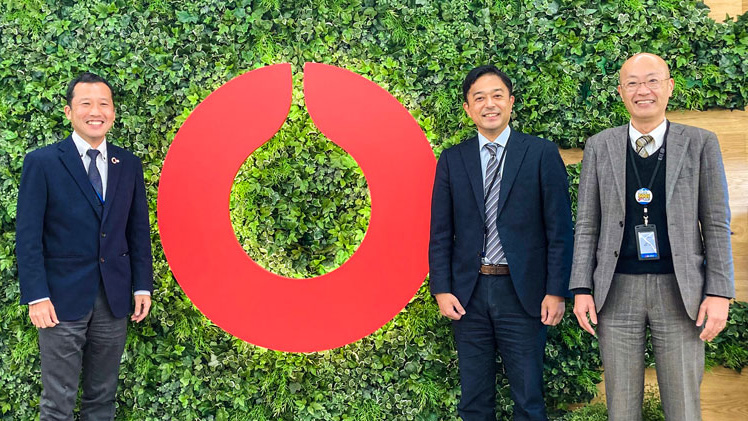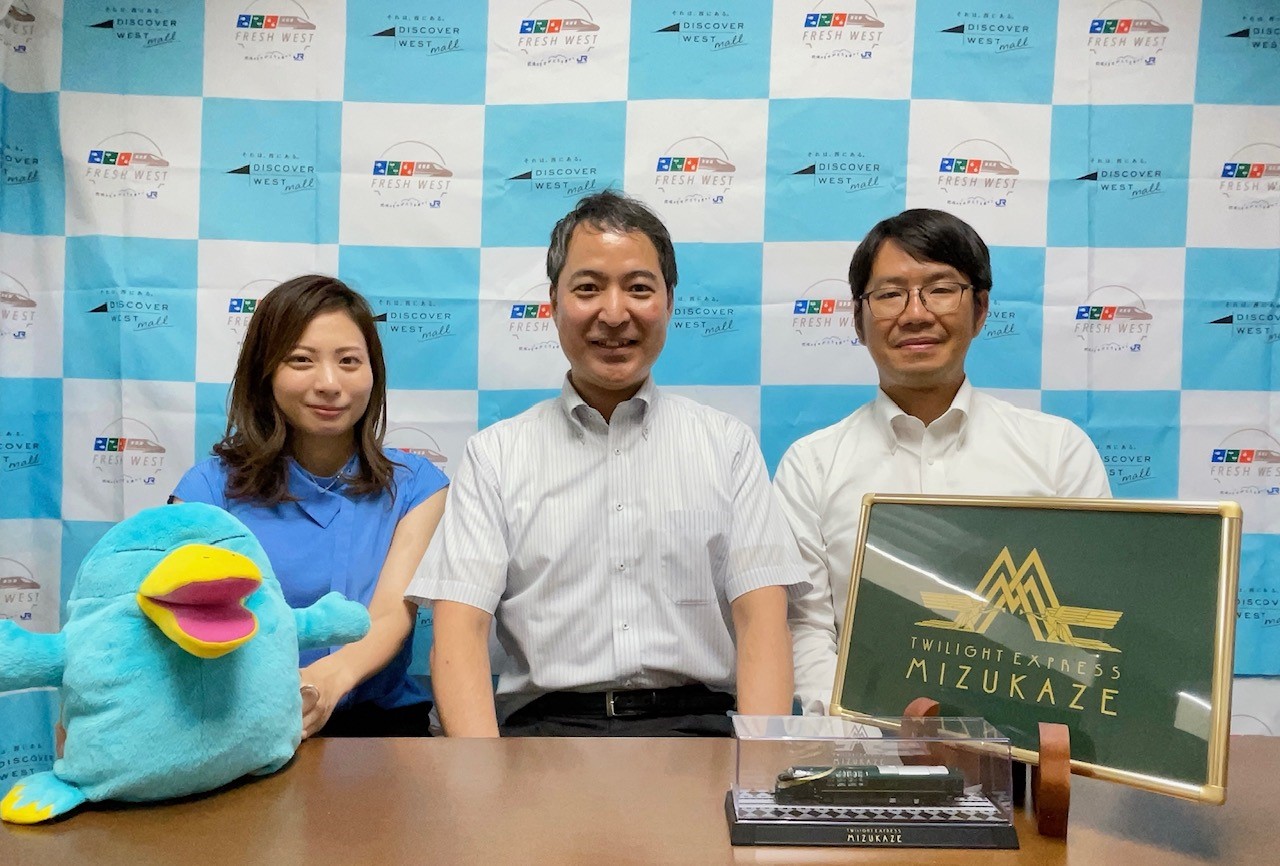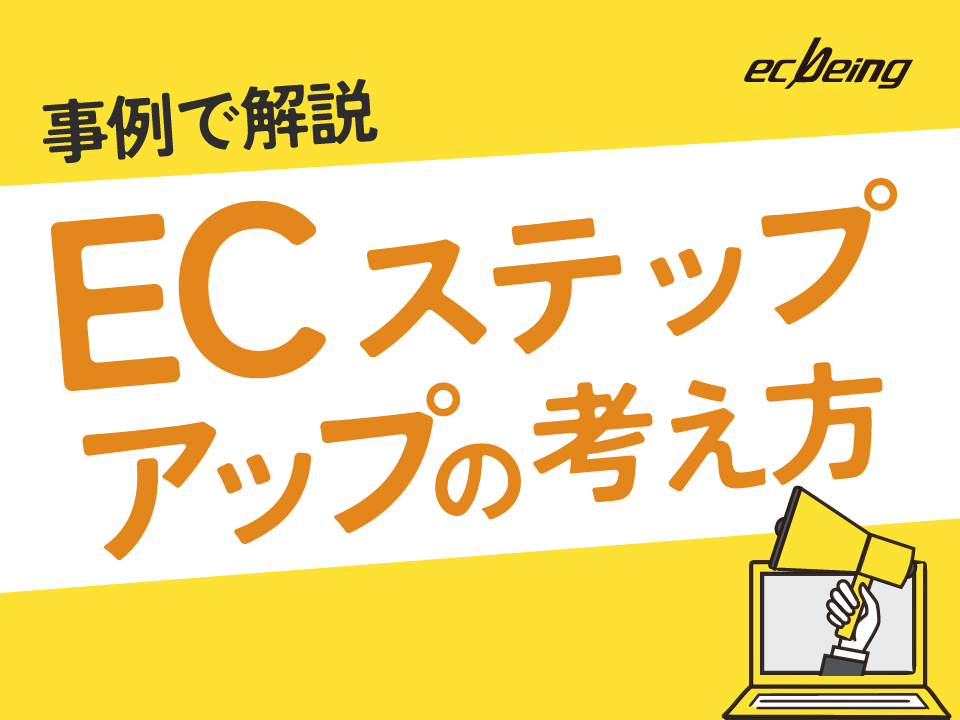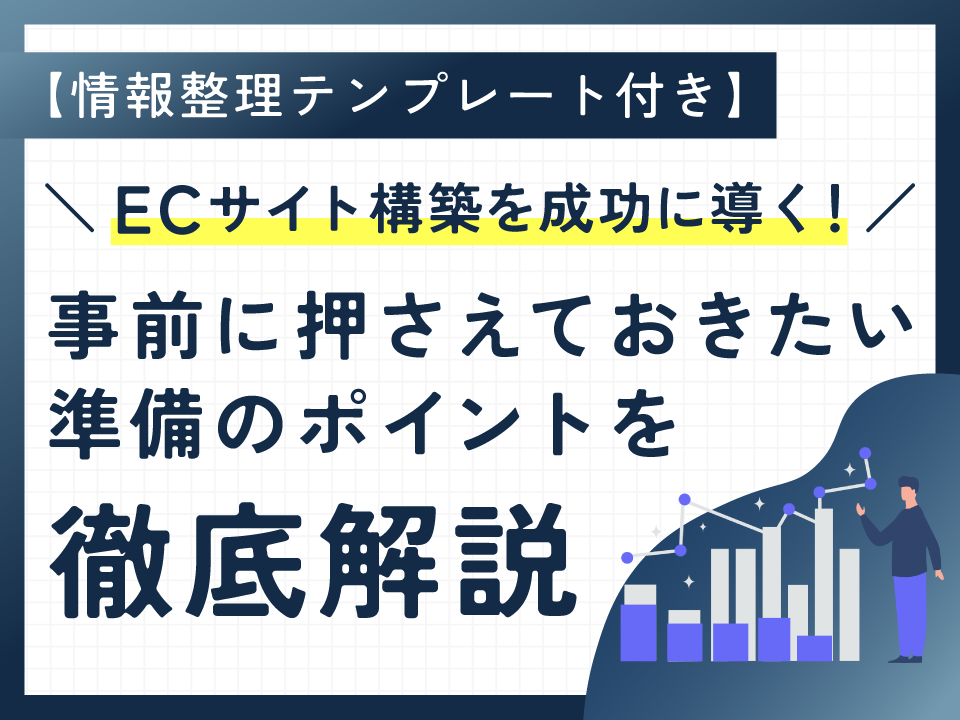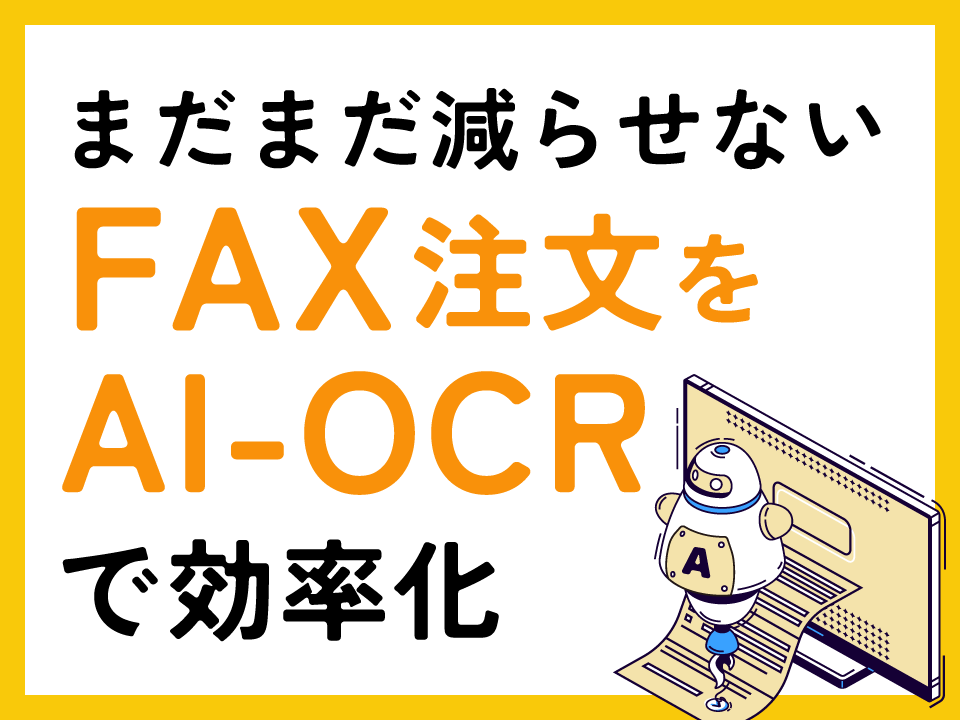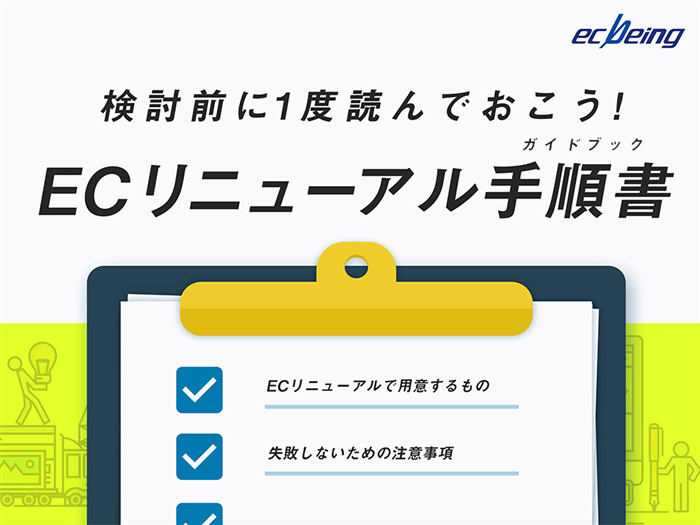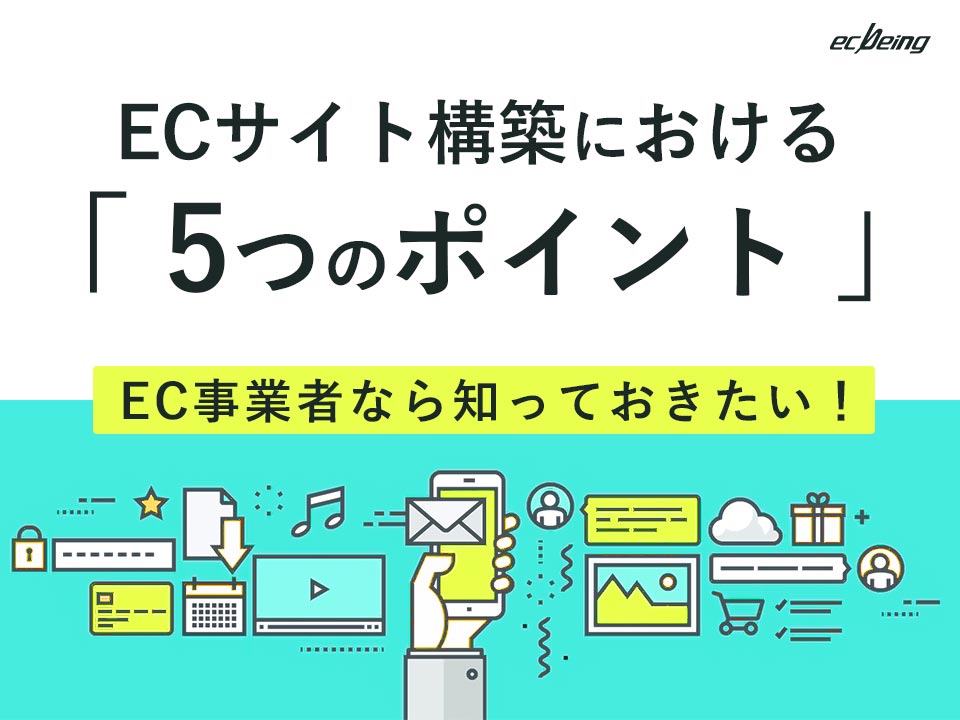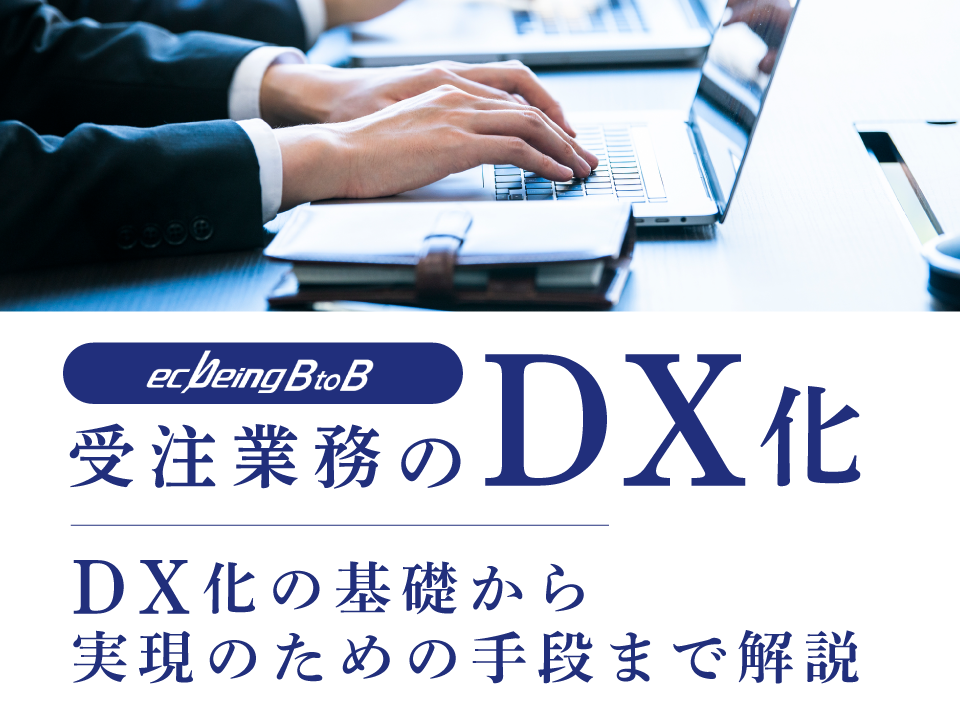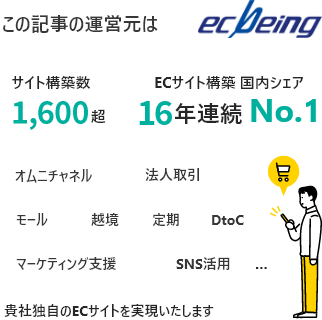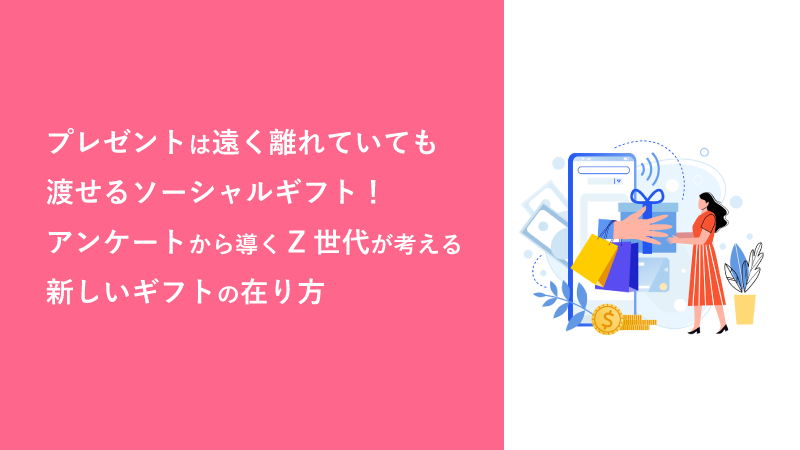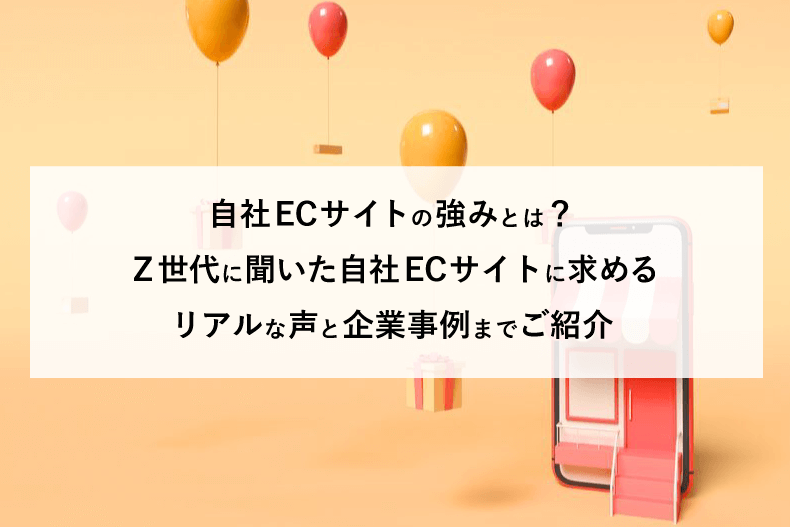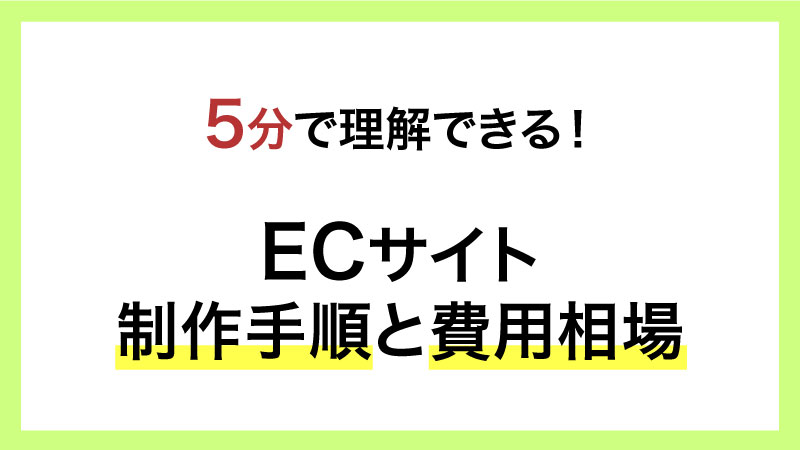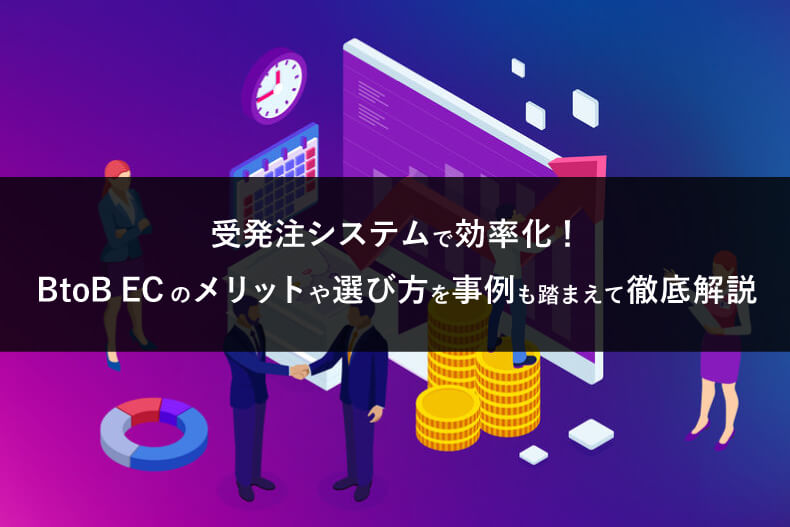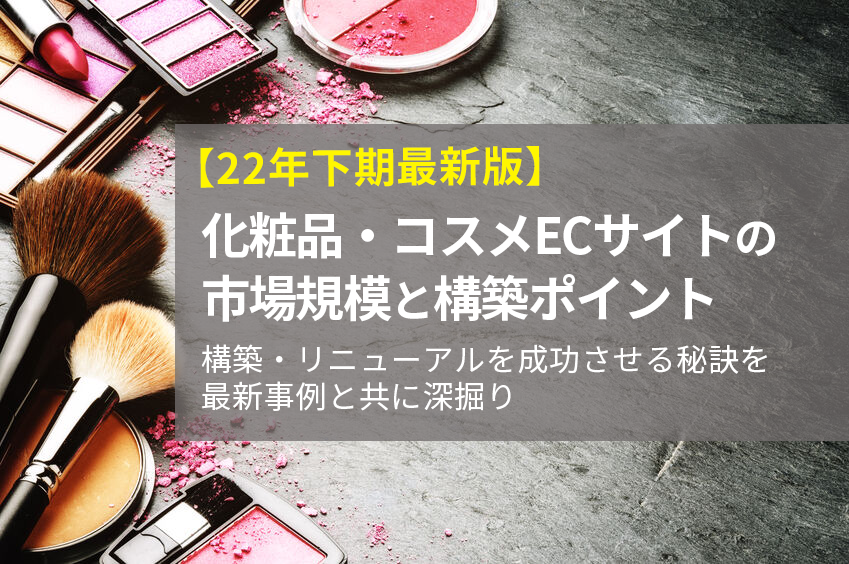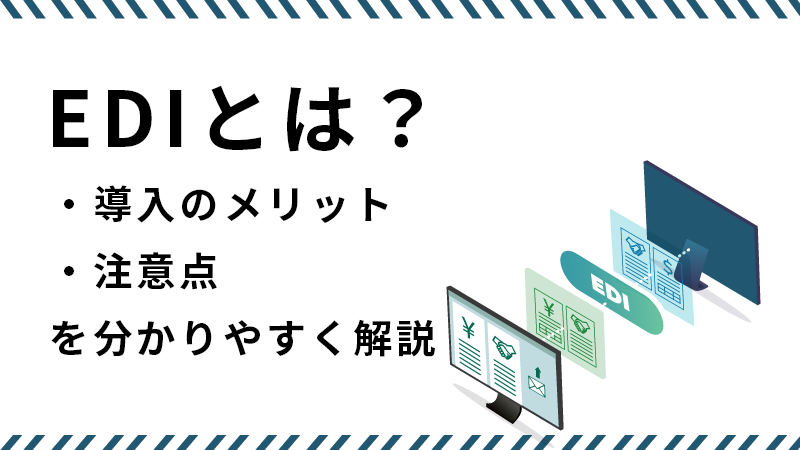- TOP
- EC�T�C�g�Ƃ�
- �ɘA����EC�̔�����ő剻�I���X�܉^�c�̉ۑ����������d�g�݂ƃV�X�e���̑I�ѕ���O����
�ɘA����EC�̔�����ő剻�I���X�܉^�c�̉ۑ����������d�g�݂ƃV�X�e���̑I�ѕ���O����
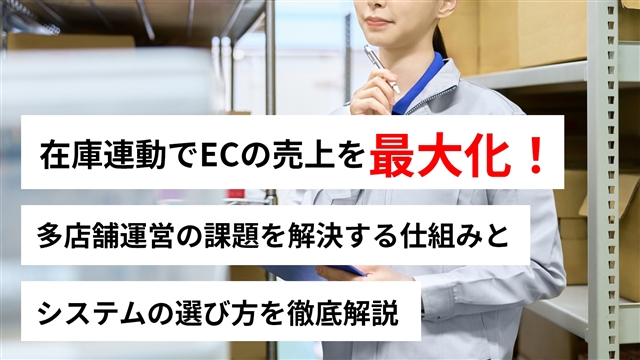
�y�V�s���Amazon�ȂǁA�����X�܂̍ɊǗ��ɂ��Y�݂ł͂���܂��H �u����z���ɂ��N���[���v��u�X�V�R��ɂ��@����v�́AEC���Ƃ̐�����W����傫�ȉۑ�ł��B ���̉����A�ɏ��������œ�������u�ɘA���v�B �{�L���ł́A�ɘA���̎d�g�݂��烁���b�g�A���s���Ȃ��V�X�e���̑I�ѕ��܂ŁAEC�̃v����������₷��������܂��B �ɊǗ����œK�����A������ő剻�����܂��傤�B
�T�N�b�Ɨ����I�{�L���̗v�_�܂Ƃ�
�u�ɘA���v���āA�����������ł����H
����EC�T�C�g��y�V�s��A���X�܂ȂǁA�����̏ꏊ�ɂ���ɏ�����ɂ܂Ƃ߂āA�����ōX�V�i�����j����d�g�݂ł��B�ǂ����ŏ��i�������ƁA�S�`���l���̍ɐ������A���^�C���Ŏ����I�Ɍ��邽�߁A���Ƃł̍X�V���s�v�ɂȂ�܂��B
�ɘA���������Ԃ̃����b�g�͉��ł����H
�u����z���ɂ��N���[���v��u�̔��@��̑����v�����{����h����_�ł��B����ɂ��ڋq�����x�����サ�A������ő剻�ł��܂��B�܂��A�ώG�ȍɊǗ��Ɩ�����������A�{�����͂��ׂ��R�A�Ɩ��Ɏ��Ԃ��g����悤�ɂȂ�܂��B
�ɘA�����n�߂�ɂ́A�ǂ���������ł����H
�A�v���[�`�͑傫��2����܂��B�@���݂�EC�T�C�g�ɊO���́u�ɘA���V�X�e���v��A�g��������@�ƁA�A�ɘA���@�\���W�����ڂ��ꂽ�uEC�T�C�g�v��V���ɍ\�z�E���j���[�A��������@�ł��B���Ƃ̍��{�I�ȉۑ�����Ə���������������Ȃ�A�A��EC�T�C�g�\�z���������߂ł��B
�y�V�s���Amazon�ȂǁA�����X�܂̍ɊǗ��ɂ��Y�݂ł͂���܂��H �u����z���ɂ��N���[���v��u�X�V�R��ɂ��@����v�́AEC���Ƃ̐�����W����傫�ȉۑ�ł��B ���̉����A�ɏ��������œ�������u�ɘA���v�B �{�L���ł́A�ɘA���̎d�g�݂��烁���b�g�A���s���Ȃ��V�X�e���̑I�ѕ��܂ŁAEC�̃v����������₷��������܂��B �ɊǗ����œK�����A������ő剻�����܂��傤�B
�ɘA���Ƃ́HEC���Ƃ̐����ɕs���ȗ��R
�ɘA���Ƃ́A�����̔̔��`���l���i����EC�T�C�g�AEC���[���A���X�܂Ȃǁj�ɓ_�݂��鏤�i�ɂ̏����ꌳ�Ǘ����A�����œ����E���f������d�g���̂��Ƃł��B
�Ⴆ�A����EC�T�C�g�ŏ��i��1���ꂽ�ꍇ�A���̏�����ɃV�X�e���ɔ��f����A�y�V�s���Amazon�A���X�܂̍ɐ��������I��1����܂��B
����ɂ��A�ǂ̃`���l�����璍���������Ă��A��ɍŐV�̐������ɐ���S�`���l���ŋ��L���邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂��B
�y�}���F�ɘA���̎d�g�݃C���[�W�z
�]���̎��Ƃɂ��ɊǗ��ł́A�^�C�����O����̓~�X���������܂���ł����B�������A�̔��`���l���̑��l���Ə���҃j�[�Y�̕��G�����i�ތ���ɂ����āA���́u�Ɂv�̏������A���^�C�������m�ɊǗ����邱�Ƃ́A�ڋq�̌��̌���Ǝ��ƌ������̗��ʂ���AEC���Ǝ҂��ŗD��Ŏ��g�ނׂ��o�c�ۑ�̂ЂƂƂ�����ł��傤�B
EC�T�C�g�ɍɘA��������5�̃����b�g
�ɘA�������邱�ƂŁA��̓I�ɂǂ̂悤�ȃ����b�g��������̂ł��傤���B�����ł͑�\�I��5�̃����b�g�����Љ�܂��B
�����b�g1�F����z���i���i�j�̖h�~�ɂ��ڋq�����x�̌���
�蓮�ł̍ɍX�V�ōł��|���̂��u����z���v�ł��B���������ɂ�������炸���i��ł��Ȃ����Ԃ́A�ڋq����̐M����傫�����Ȃ��܂��B�ɘA���V�X�e��������A�ɐ������A���^�C���őS�`���l���ɔ��f����邽�߁A�l�דI�Ȕ���z�����X�N������Ȃ��[���ɋ߂Â��邱�Ƃ��ł��A�ڋq�����x�̌���Ɍq����܂��B
�����b�g2�F�̔��@����̍팸�ɂ�锄��A�b�v
�u�{���͂܂��ɂ�����̂ɁA�X�V���Ԃɍ��킸�w�ɐ�x�\���ɂȂ��Ă����v�Ƃ����o���͂���܂��H����́A�{��������͂�������������u�̔��@��̑����v�ł��B�ɘA���ɂ��A�ɂ�������肷�ׂẴ`���l���Ŕ̔����p���ł��邽�߁A�@�����h���A����̍ő剻�ɍv�����܂��B
�����b�g3�F�ɊǗ��Ɩ��̎������E������
�e���[���̊Ǘ���ʂɃ��O�C�����čɐ����蓮�ōX�V�����Ƃ́A���Ɏ�ԂƎ��Ԃ�������܂��B�ɘA��������A���������ώG�ȍ�Ƃ����ׂĎ���������邽�߁A�S���҂͖{�����͂��ׂ��}�[�P�e�B���O��ڋq�Ή��A���i���Ƃ������R�A�Ɩ��Ɏ��Ԃ��g�����Ƃ��ł��܂��B
�����b�g4�F�f�[�^�Ɋ�Â������m�Ȕ����E���Y�v��
���ׂẴ`���l���̍ɂƔ̔��f�[�^���ꌳ�Ǘ����邱�ƂŁA�S�̂̍ɏ┄��؏��i�𐳊m�ɔc���ł��܂��B����ɂ��A����o���ɗ���̂ł͂Ȃ��A�f�[�^�Ɋ�Â����œK�Ȕ�����Y�v��𗧂Ă邱�Ƃ��\�ɂȂ�A�ߏ�ɂ⌇�i�̃��X�N��ጸ���܂��B
�����b�g5�F���X�܂�EC�̘A�g�iOMO�j�ɂ��ڋq�̌��̌���
���X�܂�POS���W�V�X�e���ƍɂ�A�������邱�ƂŁAEC�T�C�g��œX�܂̍ɏ��m�F�ł����悤�ɂ�����AEC�ōw���������i��X�܂Ŏ���悤�ɂ�����Ƃ������uOMO�iOnline Merges with Offline�j�v�{�������₷���Ȃ�܂��B����ɂ��A�ڋq�̗���������I�ɍ��܂�A�u�����h�S�̂̃t�@�����𑣐i���܂��B
�����O�ɒm��ׂ��f�����b�g�ƒ��ӓ_
�����̃����b�g������ɘA���ł����A�����O�ɂ͈ȉ��̓_���������Ă����K�v������܂��B
- �������E�^�p�R�X�g�̔���
�ɘA���V�X�e���̓����ɂ́A������p�⌎�z���p���Ƃ������R�X�g���������܂��B���Ђ̎��ƋK�͂�\�Z�Ɍ��������V�X�e����I�Ԃ��Ƃ��d�v�ł��B - ���Ɩ��t���[�̌��������K�v�ȏꍇ������
�V�X�e���̓����ɔ����A����܂ł̍ɊǗ�������̋Ɩ��t���[��ύX����K�v���o�Ă���ꍇ������܂��B�����O�ɎГ��ł̘A�g�̐��𐮂��A�X���[�Y�Ȉڍs�v��𗧂Ă邱�Ƃ������̌��ƂȂ�܂��B
�y���s���Ȃ��z�ɘA���V�X�e���̑I�ѕ� 3�̃|�C���g
�ł́A���ЂɍœK�ȍɘA���V�X�e���͂ǂ̂悤�ɑI�ׂ悢�̂ł��傤���B�����ł́A��r���������Ō������Ȃ�3�̃|�C���g��������܂��B
�|�C���g1�F���Ђ̔̔��`���l���ɑΉ����Ă��邩
�܂��m�F���ׂ��́A���Ђ����p���Ă���A���邢�͏����I�ɗ��p����\���̂���̔��`���l���iEC�J�[�g�V�X�e���AEC���[���APOS���W�Ȃǁj�ɃV�X�e�����Ή����Ă��邩�ł��B�Ή��͈͂������ƁA���������������Ă��ꕔ�̍ɂ͎蓮�Ǘ��̂܂܁A�Ƃ������ƂɂȂ肩�˂܂���B
�|�C���g2�F���ƋK�͂⏫���̊g�����ɍ����Ă��邩
�V�X�e���̋@�\�◿���v�����͗l�X�ł��B���݂̎����⏤�i�������łȂ��A����̎��Ɗg����������A�����\�͂�@�\�̊g�������l�����đI�т܂��傤�B�ŏ��͏��K�͂Ŏn�߂āA���Ƃ̐����ɍ��킹�ăv�������A�b�v�O���[�h�ł���V�X�e�������z�I�ł��B
�|�C���g3�F�T�|�[�g�̐��͏[�����Ă��邩
�V�X�e���Ƀg���u���͂����̂ł��B������̍ۂɁA�d�b��[���Őv���ɑΉ����Ă����T�|�[�g�̐��������Ă��邩�͔��ɏd�v�ł��B�������̐ݒ�T�|�[�g�̗L���Ȃǂ��܂߁A���S���ĉ^�p��C������x���_�[��I�т܂��傤�B
�ɘA������������2�̃A�v���[�`
�����܂ōɘA���̏d�v����V�X�e���̑I�ѕ���������Ă��܂������A���̎������@�ɂ͑傫��������2�̃A�v���[�`������܂��B�ǂ��炪���ЂɂƂ��čœK���A���Ђ��������������B
�A�v���[�`1�F������EC�T�C�g�Ɂu�ɘA���V�X�e���v������
���݉^�p���Ă���EC�T�C�g�͂��̂܂܂ɁA�O���̍ɘA���V�X�e���i�T�[�r�X�j���_�A�e�̔��`���l���ƘA�g��������@�ł��B��r�I�������X�s�[�f�B�ɓ����ł���_�������b�g�ł����AEC�T�C�g�ƃV�X�e�����ʁX�ł��邽�߁A�A�g�̍ۂɎd�l��̐�����������A�f�[�^�̓�d�Ǘ����K�v�ɂȂ����肷��P�[�X������܂��B�ΏǗÖ@�I�ȉ������ƂȂ肪���ŁA���{�I�ȉۑ肪�c��\�����ۂ߂܂���B
�A�v���[�`2�F�ɘA���@�\���W�����ڂ��ꂽ�uEC�T�C�g�v���\�z����
�����ЂƂ̕��@�́A�ɘA���⑽�X�ܓW�J��O��Ƃ��Đv���ꂽEC�v���b�g�t�H�[����I�сAEC�T�C�g���̂����j���[�A���E�V�K�\�z�����A�v���[�`�ł��B���������͑O�҂����傫���Ȃ�\��������܂����A�V�X�e���ƃT�C�g����̉����Ă��邽�߁A�V�[�����X�ň��肵���ɘA���������ł��܂��B�܂��A�ɊǗ������łȂ��A�Ǘ���ڋq�Ǘ��A���i�Ǘ��Ƃ�������Ɩ��S�̂��ꌳ���ł��邽�߁A���ƑS�̂̋Ɩ����������I�Ɍ��コ���邱�Ƃ��\�ł��B
�����I�Ȏ��Ɗg���AOMO�̂悤�ȍ��x�Ȏ{���W�J������ɓ����Ȃ�A�ꓖ����I�ȃV�X�e���̒lj��ł͂Ȃ��A���Ƃ̊�ՂƂȂ�EC�v���b�g�t�H�[�����̂��̂����������Ƃ��A���ʓI�ɍł������Ό��ʂ̍����I���ƂȂ�ł��傤�B
�܂Ƃ�
�{�L���ł́A���X�܉^�c�̉ۑ����������u�ɘA���v�̏d�v���ɂ��ĉ�����܂����B �ɘA���́A����z����@�����h���Ŕ�����ő剻���A�ɊǗ��̎������ɂ���ăR�A�Ɩ��ɏW���ł�������������܂��B ���̎����ɂ́u�O���V�X�e���̓����v�ƁuEC�T�C�g�̍č\�z�v��2�̕��@������܂����A���Ƃ̍��{�I�ȉۑ�����Ə���������������Ȃ�AEC�v���b�g�t�H�[�����̂̌��������ł��L���ł��B �ɊǗ��́A���͂�P�Ȃ�u���v�ł͂Ȃ��A��������E����u�U�߁v�̌o�c�헪�ł��B�����A���Ȃ����ɂ̉ۑ�����{����������A�r�W�l�X��͋����������������Ƃ��l���Ȃ�A������EC�T�C�g�݂̍������������D�̃^�C�~���O��������܂���B

�������ecbeing
 03-3486-2631
03-3486-2631- �c�Ǝ��� 9�F00�`19�F00