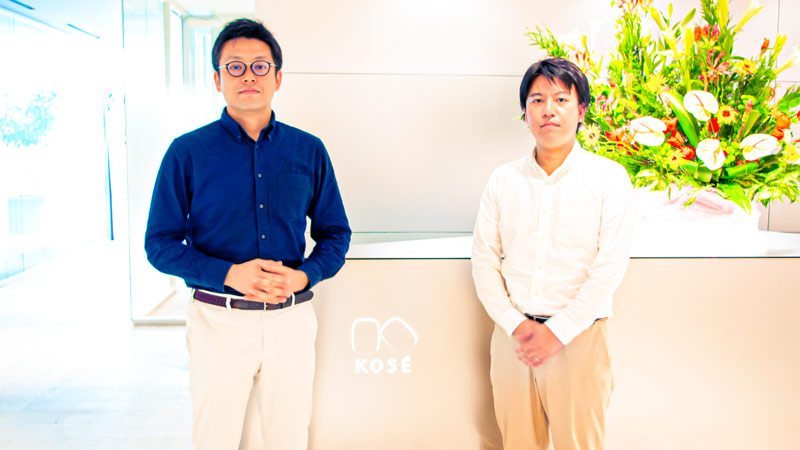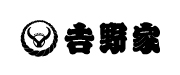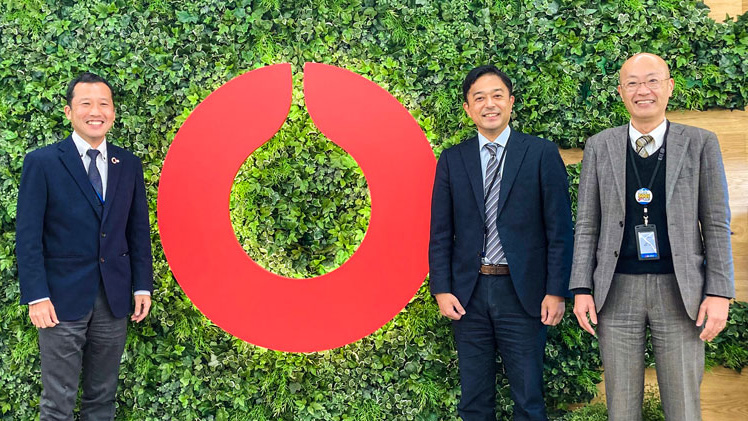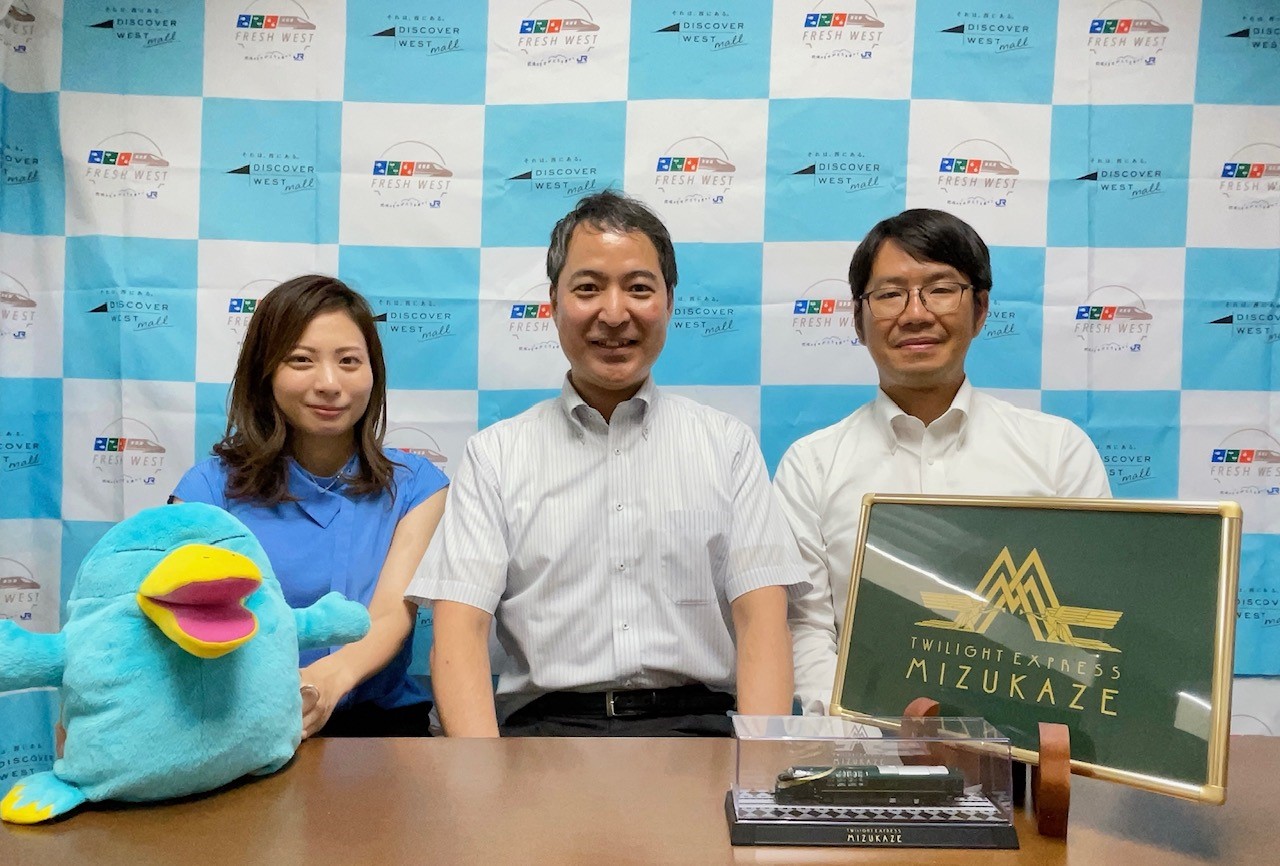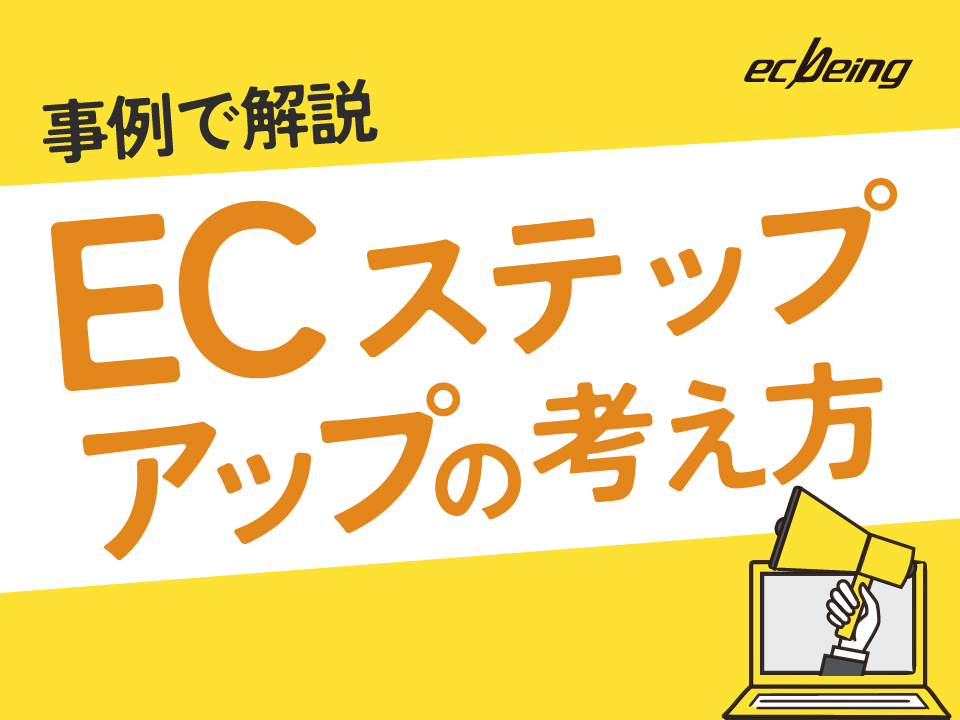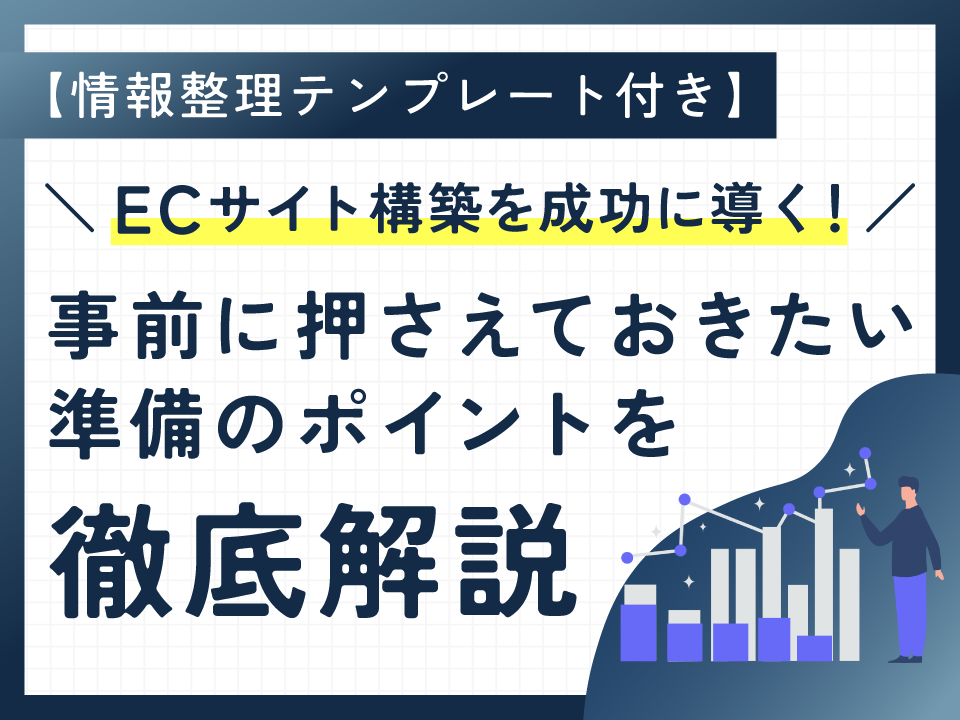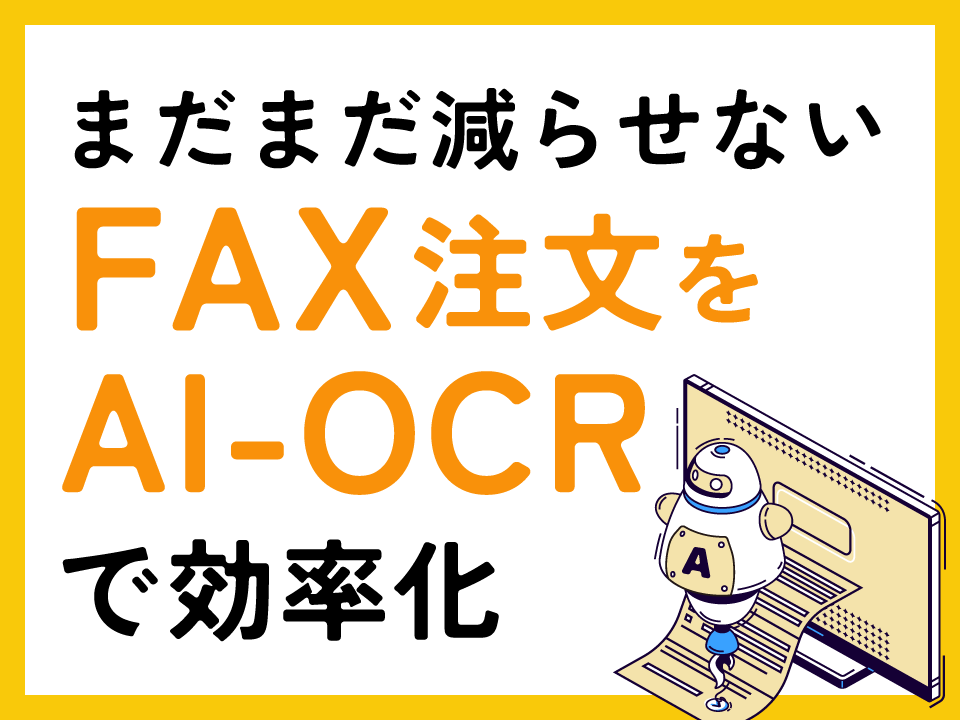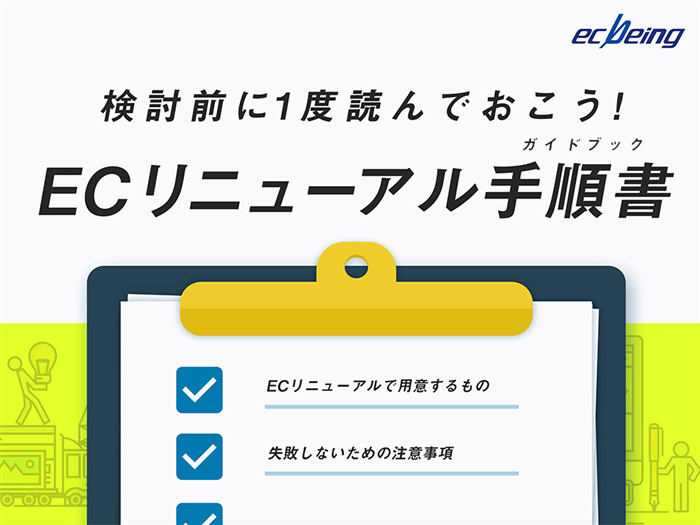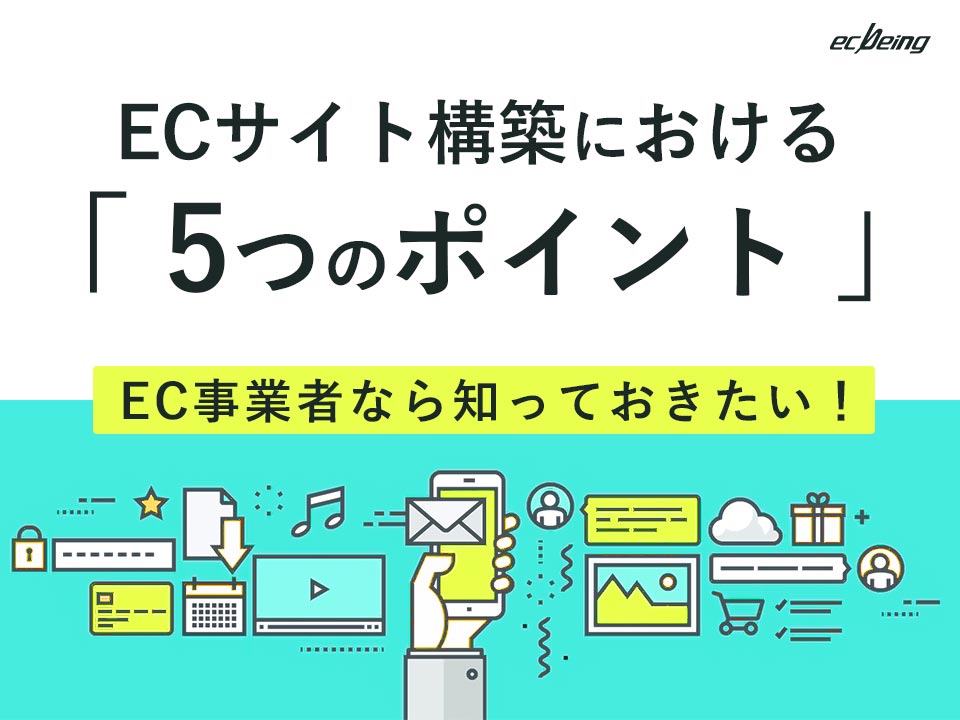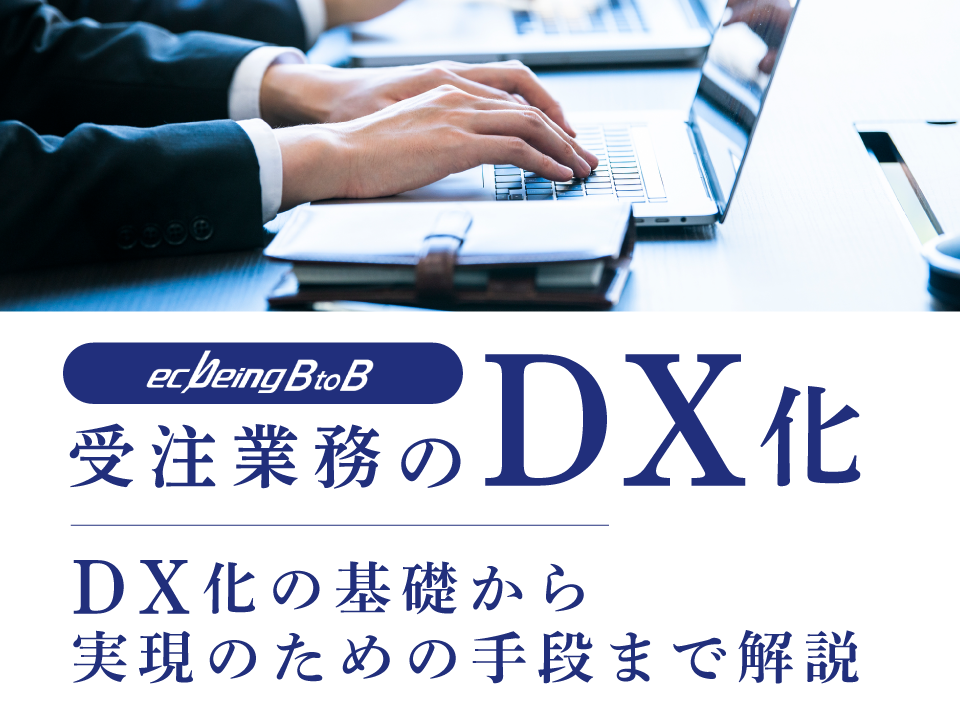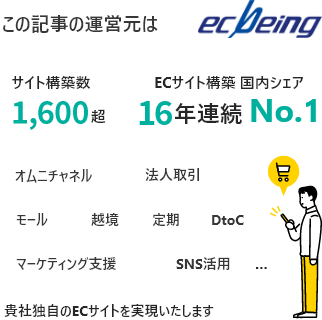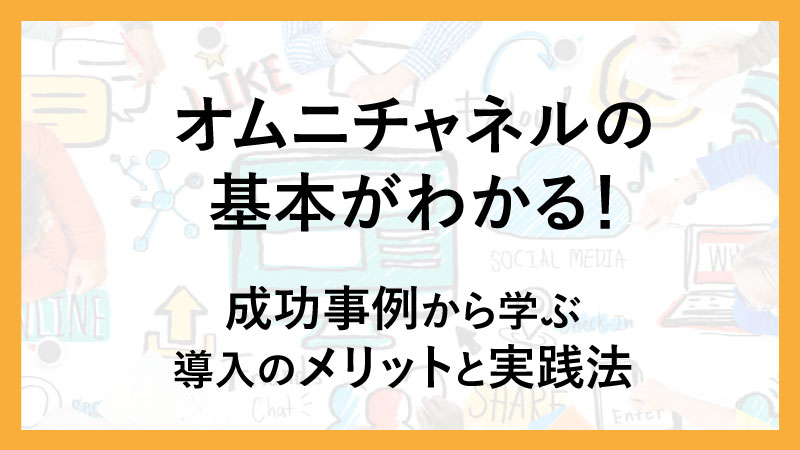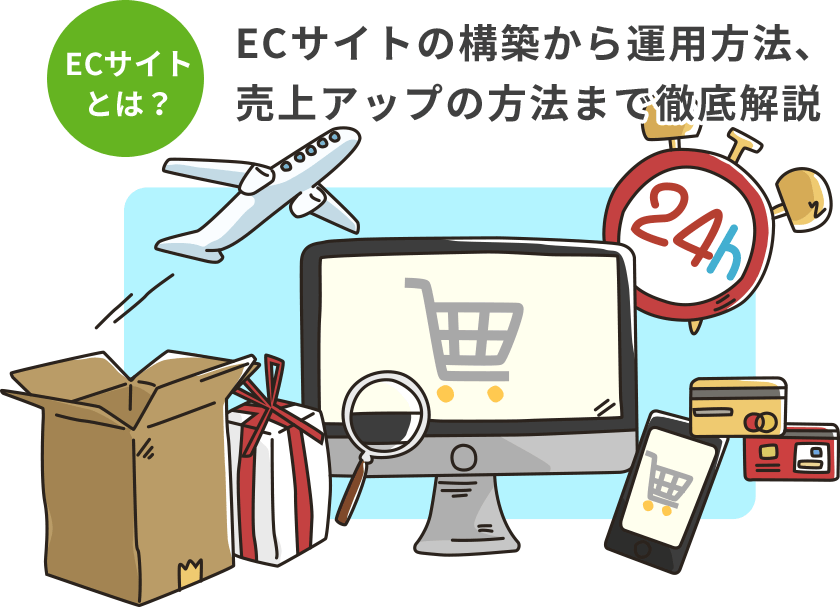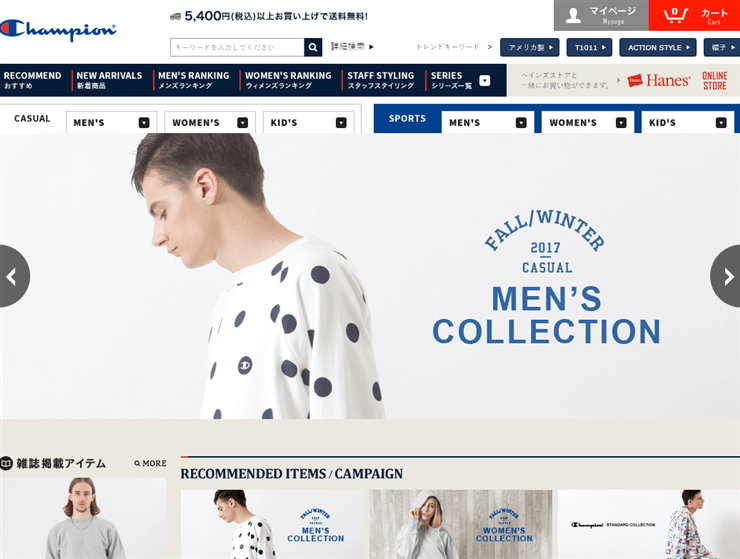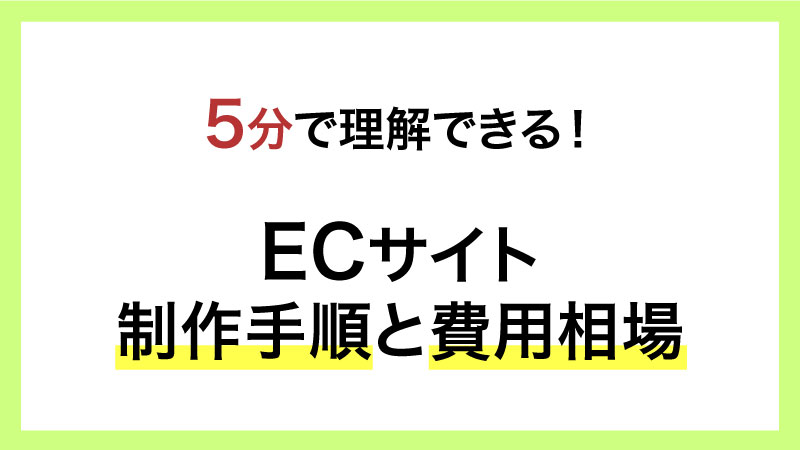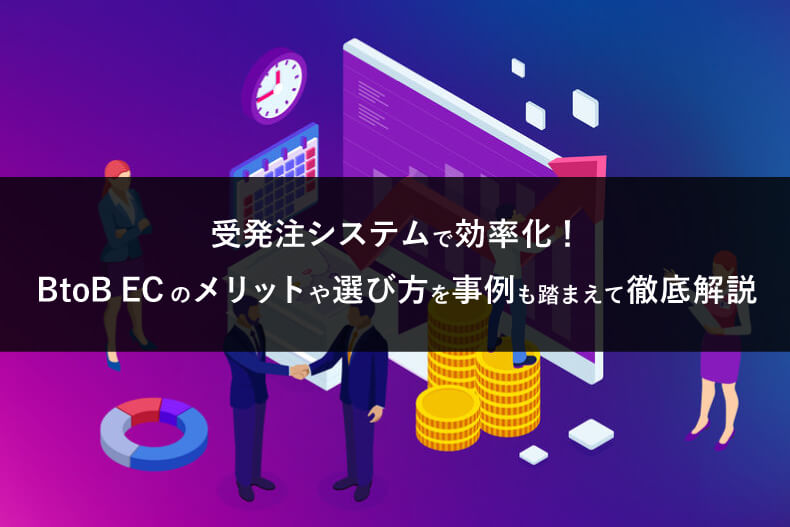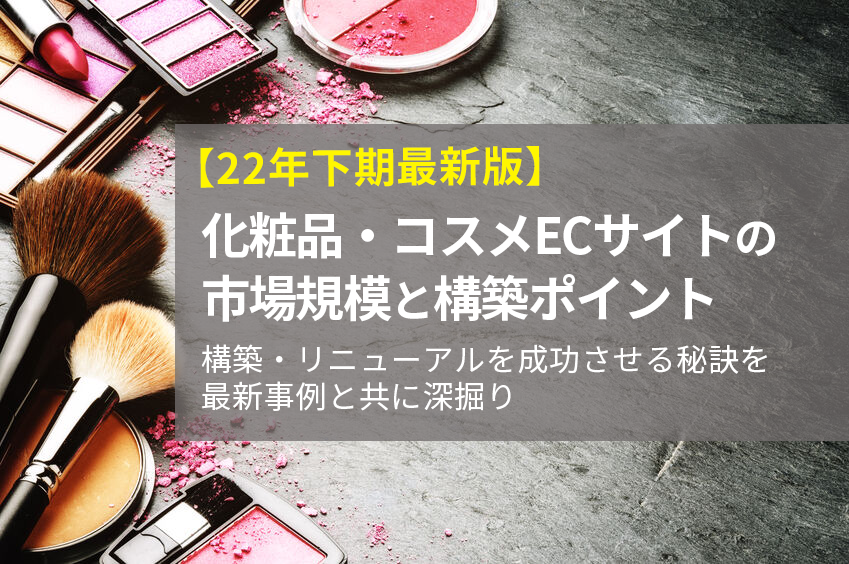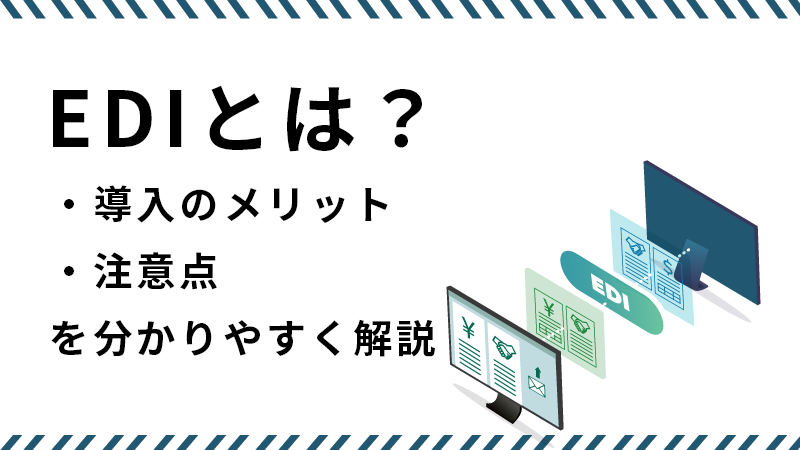- TOP
- EC�T�C�g�Ƃ�
- �H�iEC����芪������Ɛ����̂��߂ɒm���Ă����ׂ��|�C���g�A������������Љ�I
�H�iEC����芪������Ɛ����̂��߂ɒm���Ă����ׂ��|�C���g�A������������Љ�I
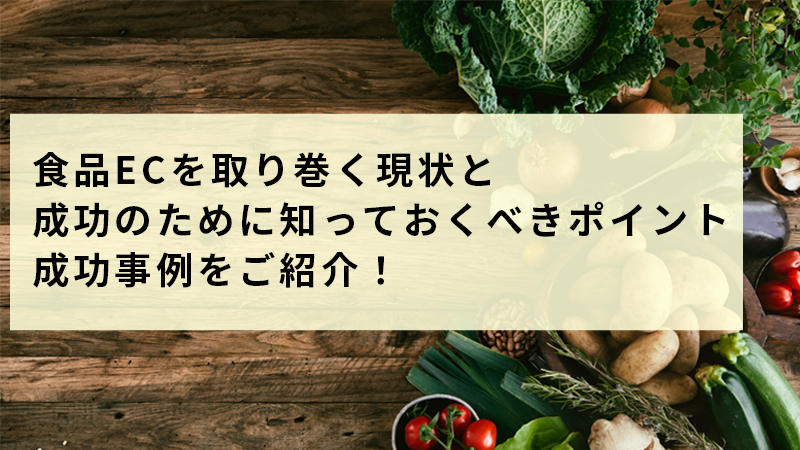
�ߔN�AEC�s�ꂪ����オ��������钆�A�H�i�ƊE�ɂ�����EC�̐Z�����ɂ͂܂��܂��ۑ肪����܂��B�H�iEC���^�c����ۂ́A�ۑ�𗝉�����ƂƂ��ɁA�����ɓ������߂̃|�C���g���������Ď��{���邱�Ƃ��d�v�ł��B
����́A�ŐV�̐H�iEC�s��̂ق��A�H�iEC�̎�ނ�ۑ�A��Ƒ��ƃ��[�U�[���̃����b�g������ƂƂ��ɉ�����܂��B
�T�N�b�Ɨ����I�{�L���̗v�_�܂Ƃ�
�H�iEC�Ƃ͂ǂ�Ȏ�ނ�����܂����H
�H�iEC�́A���t�̒ʂ��ɐH���i����舵��EC�T�C�g�ł��B�H�iEC�͂��̗p�r�ɉ����āA�L���H���i����舵����ʓI�ȐH�iEC�A�l�b�g�X�[�p�[�A����̔����EC�Ƃ�����3�̎�ނɕ������܂��B
�H�iEC�T�C�g���\�z���邱�ƂŎ��Ǝ҂������郁���b�g�͉��ł����H
�����E�̘H��啝�ɍL������A�̔����Ԃ̐������Ȃ����ߎ@��𑝂₹��A���[�U�[�ɏ��i�̖��͂��_�C���N�g�ɓ͂�����Ƃ����������b�g������܂��B
�ߔN�AEC�s�ꂪ����オ��������钆�A�H�i�ƊE�ɂ�����EC�̐Z������4%��Ƃ܂��܂��ۑ肪����܂��B���̋ƊE�ł�40%��50������EC����������Ȃ��AEC�\�z�̐�Ⴊ���Ȃ��H�i�ƊE�ł͐H�iEC���^�c����ۂ́A�ۑ�𐳂�����������ƂƂ��ɁA�����ɓ������߂̃|�C���g���������Ď��{���邱�Ƃ��d�v�ł��B
����́A�ŐV�̐H�iEC�s��̂ق��A�H�iEC�̎�ނ�ۑ�A��Ƒ��ƃ��[�U�[���̃����b�g��ecbeing���\�z����EC��������ƂƂ��ɉ�����܂��B
�H�iEC�Ƃ́H�������������3�̎��
�H�iEC�́A���t�̒ʂ��ɐH���i����舵��EC�T�C�g�ł��B�H�iEC�͂��̗p�r�ɉ����āA�L���H���i����舵����ʓI�ȐH�iEC�A�l�b�g�X�[�p�[�A����̔����EC�Ƃ�����3�̎�ނɕ������܂��B
�����ł́A�����3��ނ̐H�iEC�ɂ��Ă̈Ⴂ����������Љ�܂��B
�@ ��ʓI�ȐH�iEC
��ʓI�ȐH�iEC�́A���̂悤�ȐH�i��̔�����EC�T�C�g���w���܂��B
- ���N�H�i
- ���
- ���H�i
- ����
- ��ށ@�Ȃ�
��ʓI�ȐH�iEC�́A�����X��S�ݓX�Ƃ������̔��Ǝ҂�����EC�T�C�g�╡���̎��Ǝ҂��o�i�E�o�X����“���[���^EC�T�C�g”�Ń��[�U�[�ɏ��i��̔����܂��B
����Amazon��y�V�Ƃ��������[���^EC�T�C�g�Ŕ̔�����邱�Ƃ������A���̐�����A���i�������������_��u�����h�̔F�m������Ƃ�������肪����܂��B
�ߔN�ł́A�����X������ɐ��Y�҂�H�i���[�J�[�����[�U�[�ɒ��ڏ��i��̔�����DtoC�iDirect to Consumer�j�ƌĂ��`�Ԃ�EC�T�C�g���^�c���鎖�Ǝ҂������Ă�����A���̂悤�ȃP�[�X�ł̓��[���^EC�T�C�g�ƕ��p����`�ŁA����EC�T�C�g���^�c���Ă��鎖�Ǝ҂������Ă��Ă��܂��B
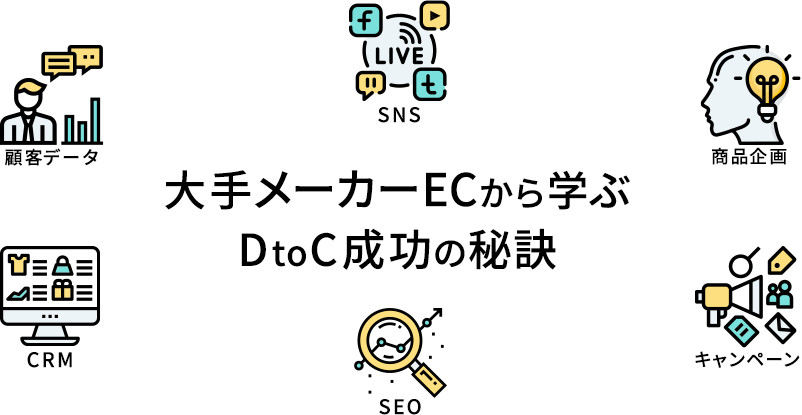
�A �l�b�g�X�[�p�[
�l�b�g�X�[�p�[�́A�C���^�[�l�b�g�Œ������āA�z����ɋ߂��X�[�p�[�}�[�P�b�g����z�B����̔��`�Ԃł��B�C�I����C�g�[���[�J�h�[�A���}�X�g�A�Ƃ������X�[�p�[�}�[�P�b�g�ƊE���e�Ђ��Y�����܂��B
�l�b�g�X�[�p�[�̓����Ƃ��āA���N�H�i����H�i�A�����Ȃǂ͂������̂��ƁA���p�i�܂Ŕ̔����Ă���_��A�w���҂��ŒZ�œ����ɏ��i������Ƃ����_���������܂��B�������A�X�܍ɂ����ƂȂ邽�ߑΉ��ł��Ȃ��G���A�����݂��邱�Ƃ�A�}�ȍɐꂪ�������Ă��܂����Ƃ��l�b�g�X�[�p�[���\�z���邤���ōl�����Ȃ�������Ȃ��|�C���g�ł��B
�܂��A�ŋ߂ł̓R���i�̉e���ɂ����X�܂������Ȃ��l�b�g�X�[�p�[���o�ꂵ�A���ڂ��W�߂Ă��܂��B
�B ����̔����EC�i�H�i�T�u�X�N�j
����̔����EC�́A����I�ɐ��N�H�i����H�i�Ȃǂ̏��i��z������̔��`�Ԃ��̗p����EC�T�C�g�ł��B����E���y�z�M�Ȃǂœ�������邱�Ƃ������T�u�X�N���v�V�����T�[�r�X���A�H�iEC�ɓ��������T�[�r�X�Ƃ������Ƃ���A�H�i�T�u�X�N�i�T�u�X�N���v�V�����T�[�r�X�j�Ƃ��Ă�܂��B
���[�U�[�����T�A�����Ȃǃv�����ɍ��킹�Ē�z�̑�����x�������ƂŁA����I�ɏ��i����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B����̔����EC�ł́A���S���ɂ���������H�ނ�L�@��ؐ��ȂǁA���X�Ƃ̍��ʉ���_���H�i�̔��X�Ŏ�������Ă���A���b�z�[�u���[�C���O�l��_�C�h�[�h�����R�l�A�����r�^�~���l�A�}���R���l�ȂǁAecbeing�ō\�z�����H�iEC�T�C�g�ł��T�u�X�N���v�V�������T�[�r�X�̈�Ƃ��ēW�J���Ă����Ɨl��������������Ⴂ�܂��B
ecbeing���\�z�����T�u�X�N���v�V�����Ή�EC����͂�����
�ڍׂ�ǂ�
2024�N�ŁF�H�iEC�̎s��K�͂�EC�����̍�
�o�ώY�ƏȂ�2024�N�ɔ��\���Ă����w�ߘa�T�N�x �d�q������Ɋւ���s�꒲�� ���x�ɂ��ƁA�����A��ނ��܂߂��H�iEC�̑S�Ă̎���ɂ�����EC�̊���������EC�����́A2023�N���_��4.29���ƂȂ��Ă��܂��B����͓������̌n����̎����ԁA������֎ԁA�p�[�c�������������EC�����Ɏ����ŒႢ�����ƂȂ��Ă���A�N�X�K�͂Ȃ�т�EC�������g�債�Ă���Ƃ͂����܂��܂��ႢEC�����ƌ��킴������܂���B
���̌n�����BtoC-EC�s��K��
| ���� | 2022�N | 2023�N | ||
|---|---|---|---|---|
| �s��K�� �i���~�j �����i�F�O�N�� |
EC���� �i%�j |
�s��K�� �i���~�j �����i�F�O�N�� |
EC���� �i%�j |
|
| �H�i�A�����A��� | 29,299 �i6.52%���j |
4.29% | 31,163 �i6.36%���j |
4.52% |
| �����Ɠd�AAV�@��APC�E���Ӌ@�퓙 | 26,838 �i5.13%���j |
42.88% | 27,445 �i2.26%���j |
43.03% |
| ���ЁA�f���E���y�\�t�g | 18,867 �i3.54%���j |
53.45% | 18,708 �i��0.84%�j |
56.45% |
| ���ϕi�A���i | 9,709 �i5.64%���j |
8.57% | 10,150 �i4.54%���j |
8.82% |
| �����G�݁A�Ƌ�A�C���e���A | 24,721 �i5.01%���j |
31.54% | 25,616 �i3.62%���j |
32.58% |
| �ߗށE�����G�ݓ� | 26,712 �i4.76%���j |
22.88% | 27,980 �i4.74%���j |
23.38% |
| �����ԁA������֎ԁA�p�[�c�� | 3,223 �i1.26%���j |
3.64% | 3,336 �i3.50%���j |
4.16% |
| ���̑� | 7,391 �i0.87%���j |
1.91% | 7,797 �i5.49%���j |
2.08% |
| ���v | 146,760 �i4.83%���j |
9.38% | 152,194 �i3.70%���j |
9.78% |
�o�ώY�Əȁw�ߘa�T�N�x �d�q������Ɋւ���s�꒲�� ���x����ɍ쐬
�������A�H�iEC��EC�����͐L�єY��ł��܂����A�H�i�W��2023�N�̎s��K�͂����Ă݂��2��9,299���~���L�^���Ă���A���Ɣ�r���Ă��K�͂̑傫������ƂȂ��Ă��܂��B�܂��O�N����̔�r�Ɋւ��Ă��A�S�Ă̕���̒��ōł��傫��6.52%�̐L�ї��������Ă��܂��B
�X�ɁA2023�N��1���ѓ�����́u�H�i�A�����A��ށv�̔N�ԕ��ώx�o��698,876�~�ƐV�^�R���i�E�C���X�����NJg��O��2019�N�Ɣ�r�����7.7%�������Ă���A���ɒ����H�i�̐L�т��傫���A���̑���ށA�َq�ށA���ޓ����L�тĂ��邱�Ƃ���EC�Ƒ����̗ǂ��H�i�̏������������Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B���̂��Ƃ�����H�iEC�͑傫�ȃ|�e���V�������߂��r�W�l�X�ƌ����Ă������ł��傤�B
�����̃|�e���V�����͂�����̂́A���̂悤�ɐH�iEC��EC�������L�єY��ł��闝�R�Ƃ��ẮA�ƊE�Ȃ�ł͂̉��L��3�̉ۑ������Ă��邩�炾�ƍl�����܂��B
- �E���N�H�i�Ȃǂ̏��ނ�EC�T�C�g���}�b�`���Ȃ�
- �E���v�ƃR�X�g���}�b�`���Ȃ�
- �E���X�܂̗������z�����Ȃ�
�����̐H�iEC��������ۑ�Ɋւ��ẮA���̃`���v�^�[�ŏڂ������Ă����܂��B
�H�iEC�T�C�g�̐�����j��3�̉ۑ�

�����ł́A�O�q�̐H�iEC��EC�������L�тȂ��v���Ƃ��čl������R�̉ۑ�ɂ��āA�ڂ������Ă����܂��B
���N�H�i�Ȃǂ̏��ނ�EC�T�C�g���}�b�`���Ȃ�
�H�iEC�T�C�g�̐�����j�ޗv���̈�Ƃ��āA���N�H�i�Ȃǂ̏��ނ�EC�T�C�g���}�b�`���Ȃ��_���������܂��B���N�H�i�͓��ɑN�x���d�v�ł���A���̕i����ۂ��߂ɂ͌��i�ȉ��x�Ǘ���v���Ȕz�������߂��܂��B�������A������������邽�߂̗①�E�Ⓚ�z���V�X�e���͍��R�X�g�ł���A�ʏ�̕����V�X�e���ł͑Ή�������ꍇ������܂��B
�܂��A���N�H�i�͏���������Z�����߁A�ɊǗ������ɓ���ł��B�����\�����O�ꂽ�ꍇ�A�p�����X���������₷���A���ꂪ���Ƃ̗��v���������܂��B����ɁA����҂͎��ۂɎ�Ɏ���Ċm�F�ł��Ȃ����߁A�I�����C���ł̍w���ɑ���s��������܂��B�ʐ^������������ł͕i�������S�ɓ`�����ꂸ�A����҂̊��҂Ǝ��ۂ̏��i�Ƃ̊ԂɃM���b�v�������邱�Ƃ�����܂��B
�����āA���N�H�i�̌`���T�C�Y���s�ψ�ł��邽�߁A�W����������A�p�b�P�[�W���O��z�����̎�舵���ɂ��H�v���K�v�ł��B����ɑΏ����邽�߂ɂ́A���x�ȕ����V�X�e���ƕi���ۏ��s���ł��B�����̉ۑ���������邽�߂ɂ́A�����I�ȕ����l�b�g���[�N�̍\�z�A���m�Ȏ����\���A����҂̐M���邽�߂̕i���ۏؑ̐������߂��܂��B
���v�ƃR�X�g���}�b�`���Ȃ�
�H�iEC�T�C�g�̐�����j�ޗv���̈�Ƃ��āA���v�ƃR�X�g�̃o�����X�����Ȃ��_���������܂��B�H�iEC�ł́A���i�̕ۑ���z���ɂ�����R�X�g�����ɍ����Ȃ邱�Ƃ������ł��B���ɗ①�E�Ⓚ���i�������ꍇ�A���x�Ǘ����K�v�ł���A�v���Ȕz�������߂��邽�߁A�①�E�Ⓚ�ݔ��̐�����z���Ǝ҂Ƃ̌_�K�{�ł��B����ɂ��A�����R�X�g������EC�T�C�g�ɔ�ׂđ啝�ɑ������܂��B
����ɁA�ɊǗ���p�����X�̖������v���������܂��B���N�H�i�̏���������Z�����߁A�ɂ��]��Δp����������A���ꂪ�R�X�g�ƂȂ�܂��B�܂��A���v�\����ɉ�]���̊Ǘ����d�v�ł����A����ɂ͍��x�ȃf�[�^���͂ƃV�X�e���̓������K�v�ł��B�����̉^�c�R�X�g�́A�������������łȂ��A�p���I�Ȕ�p�Ƃ��Ċ�Ƃ̗��v���������܂��B
����A����҂�EC�T�C�g�ł̍w���ɑ��āA���X�܂Ɠ���������ȏ�̉��i�����͂����҂��܂��B�������A��L�̂悤�ȃR�X�g�����i�ɓ]�ł����ƁA�����͂������\�������܂�܂��B���ɑ��X�[�p�[��f�B�X�J�E���g�X�g�A�Ɣ�r����ƁA���i���������ɂȂ�A����҂�����Ă��܂����X�N������܂��B
���̂悤�ɁA�H�iEC�T�C�g�ł͗��v���m�ۂ��A�R�X�g��}���邽�߂̃o�����X�����ɓ���A�����̊�Ƃ����̉ۑ�ɒ��ʂ��Ă��܂��B
���X�܂̗������z�����Ȃ�
�H�iEC�́A���X�܂̗�������ꂸ�A����EC�Ɣ�r����“���ł��E�ǂ�����ł����i���w���ł���”�Ƃ���EC�̋��݂��\���Ɋ������Ȃ��P�[�X�����邱�Ƃ��ۑ�̈�ł��B
�H�i����舵���X�[�p�[��R���r�j�́A�X�ܐ������������łȂ��A���n�I�ɂ��w�O��l�ʂ肪�����Ƃ���ȂǗ����̍����ꏊ�ɑ������邱�Ƃ���A���̂Ƃ��ɗ~�����H�i����y�ɍw���ł��܂��B
�܂��A���X�܂ł́A�N�x���Ԃ������̖ڂŊm�F���čw���ł��܂��B�����̗��R����A�������珤�i����������܂łɎ��Ԃ̂�����H�iEC�T�C�g�́A���̏��ވȏ�Ɏ��X�܂̗������邱�Ƃ�����ƌ����܂�
���X�܂ł͎�舵���Ă��Ȃ����i����舵������AEC�T�C�g����̃|�C���g��N�[�|����p�ӂ���Ȃǂ̃����b�g������Ȃ���A���X�܂𗘗p���邨�q�l��EC�T�C�g�𗘗p���Ă����������Ƃ͏o���܂���B
�H�iEC�T�C�g���\�z���邱�ƂŎ��Ǝ҂������郁���b�g

��������́A�������K�������ǂ��Ƃ͌����Ȃ��H�i×EC�����ڂ𗁂тĂ��闝�R�ƁAEC�����炱�������郁���b�g�����Ǝґ��ƃ��[�U�[���̗����̎��_���������܂��B
�����E�̘H��啝�ɍL������
�H�i����舵�����X�܂́A��q�̒ʂ藘���̍������n�ɂ��邱�Ƃ������ł��B�������A�����炱�����p���邨�q�l�͂�����x�Œ艻����Ă���Ƃ����ʂ�����܂��B�Ŋ��̉w�O�ɐH���i�X������ɂ�������炸�A�킴�킴�w�ɂ��邨�X�܂ōs�����Ƃ͂�قǂ̗��R���Ȃ������܂���B
EC�T�C�g�ɂ́A���[�U�[�͂��E�ǂ��ɂ��Ă����i�𒍕��ł���Ƃ������݂�����܂��B����܂ł͒n���̌ڋq�𒆐S�Ƀ^�[�Q�b�g�ɂ��Ă������Ǝ҂��AEC�̋��݂����������Ƃɂ�肱��܂Ōڋq�ɂȂ肦�Ȃ������S���̃C���^�[�l�b�g���[�U�[�ɃA�v���[�`���ł���悤�ɂȂ����߁A�������L���邱�Ƃ��\�ł��B
�̔����Ԃ̐������Ȃ����ߎ@��𑝂₹��
EC�T�C�g�ł�24����365�����ł�������t���\�ł��B
���[�U�[���~�����Ǝv�����Ƃ��ɂ����ɒ������ł���悤�ɂȂ邽�ߍL���헪�Ƃ��������悭�ASNS�Ō����������i��e���r�ŗ��ꂽ���i�Ȃǂ����̏�Œ�������������悤���Ȃ�܂��B�R���r�j��X�[�p�[�Ƃ�����24���ԉc�Ƃ̓X�܂Ɣ�ׂĂ������ɏ��i���K�v�łȂ��ꍇ�͗����������A���X�܂ɗ��X����邱�Ƃ�҂����@��̑����Ɍq���邱�Ƃ��ł��܂��B
���[�U�[�ɏ��i�̖��͂��_�C���N�g�ɓ͂�����
���X�܂ł͔���ꂪ�����Ă��邱�Ƃ�����A��ЂƂ̏��i���M���邱�Ƃ��e�Ղł͂���܂���B����AEC�T�C�g�ł́A���i���Ƃɏڍ׃y�[�W��p�ӂ��邱�Ƃ��ł��邽�߁A���i�T�v�����ł͂Ȃ��X�g�[���[�������Ȃ��珤�i�ŗL�̖��͂����[�U�[�Ƀ_�C���N�g�ɓ͂��邱�Ƃ��ł��܂��B
���[�U�[�������郁���b�g

���퐶�����֗��ɂȂ�
EC�T�C�g�𗘗p���邱�ƂŎ��X�܂ɑ����^�Ԏ�Ԃ��팸�ł��邽�߁A���V����ʏa�Ȃǂɂ��X�g���X���邱�ƂȂ������������邱�Ƃ��\�ł��B
�܂��A�ǂ�����ł��������\�ƂȂ�A�①�ɂ̒��g���m�F���Ȃ��瑫��Ȃ����̂𒍕��ł��邱�Ƃ���A�����Y��̐S�z�����Ȃ��A�����ꔃ���Y�ꂪ�������ꍇ�ł������ɒlj��������ł��܂��B
�H�iEC�����̏��ނƈقȂ�_�́A�I�����C���E�I�t���C���W�Ȃ��w�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�����邽�߂ɕK�v�ȏ��i����舵���Ă��邱�Ƃł��B�����������ނ�����҂��w�i��v�j�����X�܂ɔ����ɍs�����Ƃ́A���[�e�B�[���Ƃ͂������S�ɂȂ�܂��B�T�C�g��Œ�����������A����܂ŏ��i��͂��Ă��炦��EC�́A�����ɗD�ꂽ�ƂĂ����͓I�ȃT�[�r�X�Ƃ����܂��B
�ɐꂪ�������ɂ���
�ߏ��ɏ��K�͂ȃX�[�p�[�����Ȃ��A�~�������i�������Ă��čw���ł��Ȃ������o���������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂��A�䕗�̐ڋ߂��͂��߂Ƃ������R�ЊQ�ɂ���펞�ɂ́A�����K���i��������A�C���X�^���g�H�i�Ȃǂ̔������߂��K�v�ƂȂ�A�����̓X�܂Ō��i���������邱�Ƃ�����܂��B
����A�H�iEC�́A�C���^�[�l�b�g���g�������������A������EC�T�C�g����ɂ̂���X�܂�T���Ă�����������ɓ͂��T�C�g�ɒ������������܂��B���̂��߁A��{�I�ɂ͍ɐꂪ�N�������i���w���ł��܂��B
��������̎����ł���
�ݏZ�G���A�ȊO�̓��Y�i�����X�܂ōw������ꍇ�A���Y�W���J�Â����A�n���ɃA���e�i�V���b�v������Ȃǂ̏łȂ���A���n�ɑ����^�ԈȊO���肪����ł��B
���s��ŐH�ׂ��i��ATV�E�G���Ȃǂ̃��f�B�A�Ō��ė~�����Ȃ��������ł�����ɓ���Ȃ��i�����AEC�T�C�g�𗘗p���邱�ƂŊȒP�Ɏ�����_�́A���[�U�[�ɂƂ��đ傫�ȃ����b�g�ɂȂ�܂��B
�H�iEC�𐬌������邽�߂ɕK�v�ȃ|�C���g
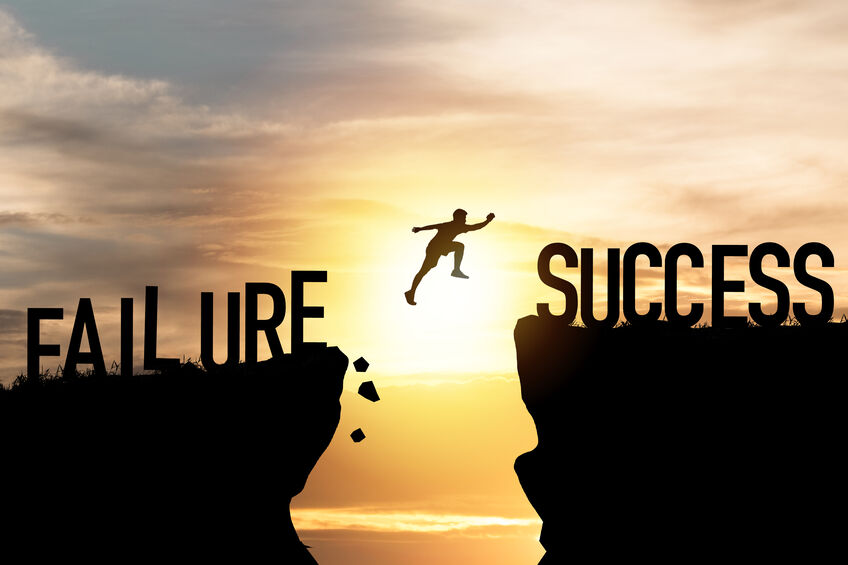
�����̍����T�C�g���\�z����
EC�T�C�g�ŏ��i���w�����Ă��炤���߂ɂ́A���[�U�[�ɂƂ��ė����̍����T�C�g���\�z���邱�Ƃ��K�v�ł��B���ɁA���X�܂̗����Ƒ傫���J���̂���H�iEC�ɂ́A�J�e�S�����Ƃɕ����ꂽ���i��������X���[�Y�ȍw�������̐v�ASNS�̊O���T�[�r�X�̃A�J�E���g�ŊȒP�ɉ���o�^��O�C�����ł���“�\�[�V�������O�C��”�̓����Ȃǂ����߂��܂��B
�I�[�v������u�ǂ��ŗ��E���Ă��邱�Ƃ������̂��v�A���͂Ƒ���s���Ȃ����Ƀ��[�U�[���g���₷���T�C�g��Nj�����悤�ɂ��܂��傤�B
���X�܂ɂ͂Ȃ��Ǝ�����ł��o��
�H�iEC�𐬌�������ɂ́A���X�܂ɂ͂Ȃ�EC�Ȃ�ł͂̓Ǝ�����ł��o�����Ƃ��d�v�ł��B�Ǝ�����ł��o�����߂̕��@�Ƃ��āA�ȉ��̎{�������܂��B
- ���n�ɑ����^�Ȃ���w���ł��Ȃ��H�ނ̔̔�
- ���V�s�ƐH�ނ̃Z�b�g�̔�
- �G�߂̌���H�ނ̔̔�
- 2��ڈȍ~�̍w���Ŏg�p�ł���N�[�|���̔z�z
- EC�T�C�g�ł̂ݗ��p�ł���|�C���g�̔z�z
�ڋq�̃j�[�Y�ɍ����{������{���ēƎ�����ł��o�����Ƃ��ł���A�V�K�ڋq��s�[�^�[�̊l���ɂȂ���Ɗ��҂ł��܂��B
�ڋq�̃��s�[�g�������߂�
���[�U�[�̃��s�[�^�[���ɒ��͂��āA�J��Ԃ��w�����Ă���郆�[�U�[���l�����邱�Ƃ���ł��B�P���ɓs�x�w���ɗ��郆�[�U�[�A������t�@������邾���ł͂Ȃ��A����w����T�u�X�N���v�V�����T�[�r�X�����邱�Ƃň��肵������グ�Ɍq���邱�Ƃ���̕��@�ł��B
���̑��A���[�U�[�̃��C�����e�B�����߂ă��s�[�g�������߂�{��Ƃ��āA���[���}�K�W���̒���z�M�A�L�����y�[���̎��{�A������T�̓W�J�Ȃǂ��������܂��B
�_����w����T�u�X�N���v�V�����ɂ��ďڂ����͂�����^
�m�E�n�E�L��������
SNS���p�Ȃǂ̃}�[�P�e�B���O�{����s��
���X�܂ł̃}�[�P�e�B���O�{��Ƃ��āATVCM��`���V�Ƃ������L����ł��ďW�q���s���̂Ɠ��l�ɁAEC�T�C�g�̏W�q�ɂ��}�[�P�e�B���O�{�K�v�ł��B
��Ȏ{��Ƃ��ẮA���i���̔��M��v�����[�V�����Ȃǂ�SNS�ōs�����[�U�[�Ƃ̃^�b�`�|�C���g�������@������܂��B
���̑��ɂ��A�r�W���A���ʂői������ꍇ�̓��[�U�[��SNS��ɓ��e��UGC�iUser Generated Contents�j�R���e���c�����p������A���ۂɏ��i���w���������[�U�[�̐��̐������[�U�[���r���[�Ƃ��ďW�߂�EC�T�C�g��Ɍ��₷���f�ڂ�����Ƃ������悤�Ȏ{����s�����Ǝ҂������Ă��܂��B
���������}�[�P�e�B���O�{����s���Ȃ���A�V�K�ڋq�̊l����ڎw���܂��傤�B
�����Ǘ��V�X�e����A�E�g�\�[�V���O�T�[�r�X����g����
EC�T�C�g�ɂƂ��ăT�C�g�I�[�v���̓S�[���ł͂���܂���B�I�[�v�����X�^�[�g�Ƒ����āA�����n�o���Ȃ���Ȃ�܂���B�I�[�v����́A�����܂ŏЉ�Ă����{��̎��{ �����ł͂Ȃ��A������t��z���ȂǗl�X�ȋƖ����������܂��B
���X�܂̐��������ꍇ�́A�s�b�L���O��Ƃ��͂��߂Ƃ����z���Ɩ����ώG�ɂȂ�����A����������������ɂ�č�����S���҂̐��ł͑Ή�������Ȃ��Ɋׂ����肷��\��������܂��B
�����������Ԃ�����邽�߂ɂ��A�Г��̐����̏ɉ����āA�����Ǘ��V�X�e���𗘗p���Ĕz���Ɩ��̌�������}��A�Ή���J�X�^�}�[�T�|�[�g�Ȃǂ̋Ɩ����O���ɃA�E�g�\�[�V���O����Ȃǂ̑����������悤�ɂ��Ă��������B
EC�\�z�v���b�g�t�H�[��ecbeing�̐H�iEC��������
����܂�1,600�ȏ��EC�T�C�g���\�z���Ă���ecbeing�ɂ͐������̐������Ⴊ����A���̒��ɂ͐H�iEC�̎�������݂��܂��B����͐H�iEC�̐�������̒�����A���ɎQ�l�ɂ��Ă�����������5�̎�����s�b�N�A�b�v���Ă݂܂����B �H�i�ƊE��EC�����͂܂��܂�4%�Ƒ��̋ƊE�Ɣ�א�Ⴊ���Ȃ����Ƃ���ɑ������Ƃ�����v���ł͂���܂����Aecbeing�ɂ͑����̐H�iEC�̍\�z���Ⴊ����܂��̂ŁA�Q�l�ɂ��Ă͂������ł��傤���B
������Ѓ��b�z�[�u���[�C���O

�u��Ȃ�ȃG�[���v�ȂǃN���t�g�r�[����̔����郄�b�z�[�u���[�C���O�l�́A�]�����p���Ă���ASP�J�[�g�ł͂ł��邱�Ƃ������Ă������Ƃ���ecbeing��EC�T�C�g�̃��j���[�A�������{���A���i�̖��͂M����Ǝ��̃R���e���c��A�]���s���Ă�������w���̋����Ȃǂ�}��܂����B���j���[�A���ȑO������w�������Ă�������̓��A98%�����j���[�A��������������p�������邱�Ƃɐ������Ă��܂��B
�_���b�z�[�u���[�C���O�l�̐�������ɂ��ďڂ����͂�����^
�m�E�n�E�L��������
������Ѓ��b�N�E�t�B�[���h
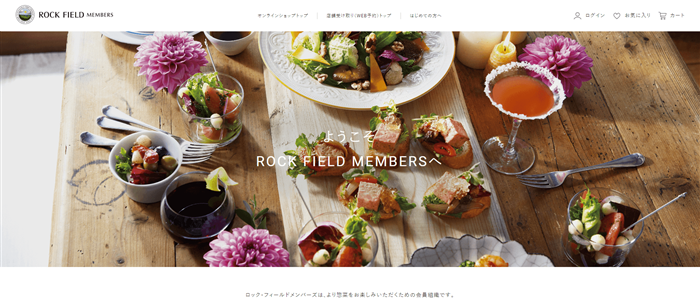
�y�̔̔����s���uRF1�v�Ȃǂ�W�J���Ă��郍�b�N�E�t�B�[���h�l�́A�X�܂�EC�̉�����̓����Ȃ�тɁA����܂ŕʁX�ɂȂ��Ă���EC�T�C�g�Ǝ��X�܂ł̎��u�����ł���\��T�C�g����ɂ����V�T�C�g��ecbeing�ō\�z���܂����B
�V�T�C�g�I�[�v����́A�O�N�̓������Ɣ�r����ƒ�������2.4�{�A���オ��3�{�ɃA�b�v����ȂljE���オ��̐������L�^���܂����B
�_���b�N�E�t�B�[���h�l�̐�������ɂ��ďڂ����͂�����^
�m�E�n�E�L��������
������ЃE�F���J��
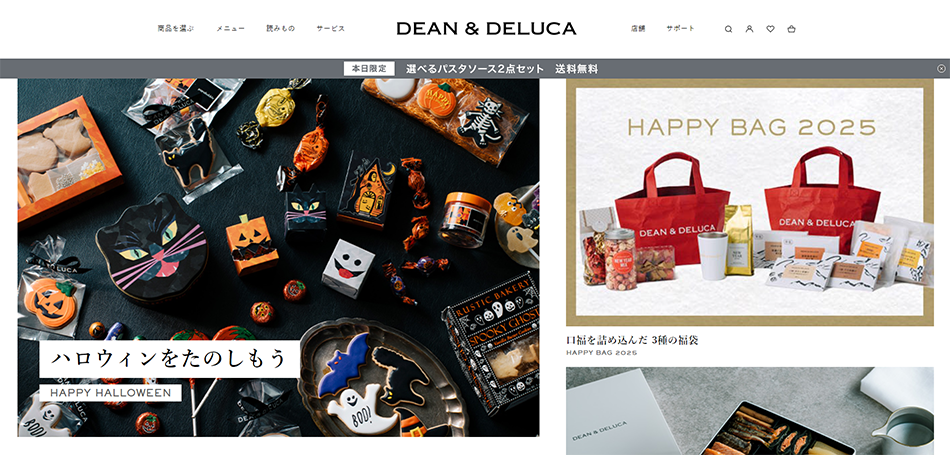
DEAN & DELUCA���̃u�����h�����L����E�F���J���l�́A�������̖��������V�X�e������ecbeing�Ƀ��j���[�A���������Ȃ��A�u�����h�T�C�g��EC�T�C�g�A�����ăI�E���h���f�B�A�����邱�Ƃɂ��u�����h���l���ő剻���͂���܂����B�܂��A���v�̍����M�t�g�̋����Ƃ��Ă��q�l���g�őg�ݍ��킹��I�ׂ�M�t�g�Z�b�g��A�ڋq�̈͂����݂̂��߂̃E�F���J���l�Ǝ��̌��ϕ��@�̓����AEC�ƓX�܂̘A�g�ɂ��I���j�`���l���̋����܂Ŏ������邱�ƂŁAEC���Ƃ����r�W�l�X�̎厲�Ƃ��Ċ��p�\�ȑ̐��𐮂��܂����B
�_�E�F���J���l�̐�������ɂ��ďڂ����͂�����^
�m�E�n�E�L��������
�}���R���������

���X����H�i�̐����̔��Ȃǂ��s���Ă���}���R���l�́A��ʏ���Ҍ�����BtoC EC�T�C�g�̃��j���[�A�������{����5��������EC������25���Ɍ��コ�����ق��A�Г��̉^�p�ʂɊւ��Ă��Ɩ����������������Ă��܂��B
�܂�BtoC�T�C�g���ŋƖ��p�̏��i�Ɋւ��ẮA�ʓrBtoB����EC�T�C�g��V�K�I�[�v�������A�����Ŏ�舵���悤�ɂȂ�܂����B
�_�}���R���l�̐�������ɂ��ďڂ����͂�����^
�m�E�n�E�L��������
������ЃV���[�b�g
����ɂ�����������َq��p���̐����E�̔����s���Ă���V���[�b�g�l�́AEC�T�C�g�����j���[�A�����ď��i�w���̓������V���v���ɂ������ƂŁA�O�N�Δ�106����CVR��B���B�܂��A���X�|���V�u�f�U�C���ɂ������ƂŋƖ����������������A�^�p������2�{�ȏ�ɂȂ�Ȃǂ̌��ʂ��������Ă��܂��B
�_�V���[�b�g�l�̐�������ɂ��ďڂ����͂�����^
�m�E�n�E�L��������
�L�[�R�[�q�[�������

�L�[�R�[�q�[�l�́A�@�\�ʂ̋����ƃZ�L�����e�B�̋����̂��߃I�[�v���\�[�X��EC�J�[�g����ecbeing�Ƀ��j���[�A���������Ȃ��܂����B���j���[�A����̓��C�����e�B�v���O���������ڋq�̈͂����݂ƍX�Ȃ�t�@������}���Ă��܂��B
�_�L�[�R�[�q�[�l�̐�������ɂ��ďڂ����͂�����^
�m�E�n�E�L��������
������ЃJ�l�J
���ِ��p���ޗ��̐������s���J�l�J�l�ƁA�x�[�J���[�̉c�Ƃ��t���T�|�[�g���Ă���J�l�J�H�i�l�́A�S���̔��������p����̔����郂�[���T�C�g�w�ς�™�x��ecbeing�ō\�z���܂����B
�g���₷�����d�������Ǘ���ʂ�V�X�e���ɂ��A�S���̃x�[�J���[�ƃp���D���ȃ��[�U�[�����Ԃ��Ƃɐ������Ă��܂��B
�_�J�l�J�l�̐�������ɂ��ďڂ����͂�����^
�m�E�n�E�L��������
�܂Ƃ�
�H�iEC�́A���ނ�EC�̑�����A���X�܂Ƃ̗��������Ȃ��Ƃ������ۑ������Ă��邱�Ƃ���A���̏��ނƔ�r����Ƃ܂��܂��Z�����Ă���Ƃ͌����܂���B
����ŁA�u�̘H��@��̊g��ɂȂ���v�u�����Ŕ̔����Ă���H�i�����n�ɍs�����Ɏ�ɓ������v�ȂǁA���Ǝґ��ƃ��[�U�[���̑o���ɑ����̃����b�g������܂��B
�����̃����b�g��O�ʂɏo�����Ƃɉ����āA���X�܂Ƃ͈قȂ�Ǝ��̎{��������ꂽ��ASNS�����p�����}�[�P�e�B���O���s�����肷�邱�ƂŁA�ۑ������W�q�A����̊g��ɓ������Ƃ��\�ł��B
�Ȃ��A�H�iEC���^�c�����ł́A���ӓ_��c������ƂƂ��ɁA�@���ɑ��������g�݂��s�����Ƃ��������܂���B���ݐH�iEC�T�C�g�̐V�K�\�z��j���[�A�����������Ă���ꍇ�́A���Љ���|�C���g�������Ȃǂ��܂߂Č�����i�߂Ă݂Ă͂������ł��傤���B
�H�iEC�̍ŐV����̂��₢���킹��\�z�̂����k�͂�����
�₢���킹��

�������ecbeing
�֘A�̂��q�l�̐�
�֘A�L��
�T���킹�ēǂ݂���
 03-3486-2631
03-3486-2631- �c�Ǝ��� 9�F00�`19�F00